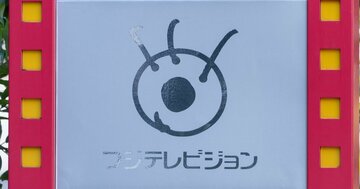現場は迫る危機を理解していた。日ごろからメディアとコミュニケーションしている報道部門は一触即発の報道状況を肌で感じていたに違いない。たが、肝心のトップとの認識のズレが埋まらないまま、第一回会見に至ってしまった。
港氏はあくまで、社員の直接関与という週刊誌の誤報に反論することにこだわり、一方で、「説明」は遅れたものの、自身ら幹部の対応に問題はなかったと信じこんでいた。冒頭の通り、会見で「謝罪」した認識もなかった。
ここで週刊誌報道からの流れを振り返って頂きたい。
19日 女性セブン、中居氏が「女性トラブル」と初報。
26日 週刊文春、中居氏の「性的トラブル」でフジテレビ社員が会食設定と記事(第1弾)。
27日 フジテレビ、「当該社員は会の設定を含め一切関与していない」と否定コメント。
2025年1月
8日 週刊文春、フジテレビ幹部が「女性の訴えを握りつぶした」と記事(第2弾)。
9日 中居氏、「トラブルがあったことは事実」と公式サイトで認める。
14日 大株主の米投資ファンド、「第三者委員会調査を要求」と報道。
15日 フジテレビ、「昨年より外部弁護士を入れ事実確認の調査を開始」とコメント。
16日 週刊文春、「別の被害者もいた」と記事(第3弾)。
17日 フジテレビ、第1回会見。取材制限で”閉鎖会見”と非難を受ける。
18日 トヨタ自動車や日本生命保険など大手スポンサー、一斉にCM差し止めへ動く。
第三者委員会が指摘した
失敗の原因とは
フジテレビ問題の炎上を招いた危機管理上のミスについて、筆者はこれまで三点を指摘してきた。
(1)根拠を示さずに社員関与の疑惑を全面否定した。
(2)事態拡大を恐れた”閉鎖会見”でメディアを敵に回した。
(3)内部調査を開示せず、独立性の高い第三者委員会調査も否定、隠ぺい疑惑を招いた。
端的に言えば、アカウンタビリティー(説明責任)を果たす覚悟と準備が出来ていなかったのだ。
第三者委員会の分析とも一致している。
(1)については、事実究明が完了していない段階でその場しのぎの会見対応がなされた、と手厳しい。質疑応答で「調査委員会に委ねる」と回答を避ける場面を連発したことで、透明性に欠ける印象を与えた、ともしている。
(2)については、フリー記者からの人権侵害発言やテレビの生放送による被害者特定の恐れが背景にあったようだが、第二回会見から時間差配信を導入したことを考えると、理由にならない。報道局長がメディア側の反発の恐れが高いことへの懸念を表明したが、役員判断で予定通り実施された。
(3)については、そもそも内部調査が杜撰(ずさん)で、報道対応の必要にせまられて急遽、中居氏を含む関係者へのヒアリングなどが行われたが、被害者女性との対話の機会もないまま、ほぼ無策で会見に臨むことになったようだ。