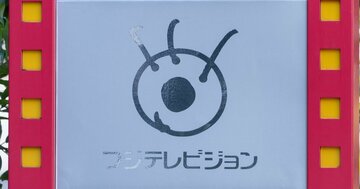筆者は何度か、経営判断の根拠となったであろう事前の内部調査の公表を勧めてきたが、結果としてまとまったものは存在しなかったようだ。正直、あきれている。
また、外部専門家を入れた調査委員会の組成が検討されていたものの、独立性の高い第三者委員会まで踏み込む判断が遅れた。結果、フジテレビの自浄作用に期待できないと評価されてしまった。
総括として、第三者委員会は「思慮の浅い危機管理」を根本原因とした。(1)初動調査の遅れ、(2)危機への認識の甘さ、責任者不在の無責任体制、(3)事前調査・専門家からの助言の欠如を上げている。
幕引きの条件は
そろったが…
フジテレビ問題の具体的な”落としどころ” として、筆者は以下の4点をあげていた。
(1)可能な限り踏み込んだ調査結果の公表(第三者委員会側と要調整)
(2)女性への直接謝罪(トップ自身が対面で経緯説明と謝罪。出来れば会見前)
(3)過去の経営陣の責任明確化(関心の高い日枝久取締役相談役の処遇を含む)
(4)社内モニタリング体制の構築(改革の進捗を監視・公表する仕組みの導入)
本記事を執筆している4月1日昼の段階では、まだメディア、世論の受け止めは固まっていないと思われるが、時期尚早とのそしりを覚悟であえて評価してみよう。
(1)については、第三者委員会が「『業務の延長線上』における性暴力」の認定まで踏み込み、一連の経緯の背景を明らかにし、経営陣の責任を厳しく追及したことで、一定の評価を得られたのではないか。
被害女性が代理人弁護士を通して発表したコメントでは、「昨日第三者委員会の調査報告書が公表されてその見解が示され、ほっとしたというのが正直な気持ちです 」などと、調査へのポジティブな評価が述べられている。
(2)については、調査中のため直接謝罪は実現しなかったが、清水賢治社長は会見で繰り返し、「被害女性の心に寄り添うことができなかった」などと謝罪し、元社員の苦しみへの配慮を示した。
(3)については、フジサンケイグループ代表を含めた日枝氏の辞任が大きく報じられている。影響力が残るのではないか、との疑念は当然あるだろう。旧経営陣や幹部の処分については関心が高い。
(4)については、さまざまな改善対策の導入が説明された。実効性があがるかどうか、対外的にどう開示していくかが問われることになろう。
結論としては、再生への期待を込めて”合格点”としたい。ようやく信頼回復の入り口に立ったと言えるのではないか。特に、たった一人で会見をしのぎ切った清水社長の胆力には敬意を表したい。
次は、コマーシャルを見合わせているスポンサー企業の対応が注目される。