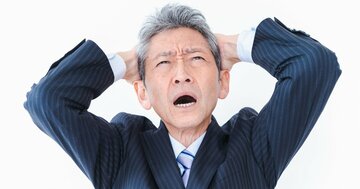生前贈与が老後破産の引き金に? 節税より大切な“家族とお金”
相続は誰にでも起こりうること。でも、いざ身内が亡くなると、なにから手をつけていいかわからず、慌ててしまいます。さらに、相続をきっかけに、仲が良かったはずの肉親と争いに発展してしまうことも……。そんなことにならにならないように、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)の著者で相続の相談実績4000件超の税理士が、身近な人が亡くなった後に訪れる相続のあらゆるゴチャゴチャの解決法を、手取り足取りわかりやすく解説します。
本書は、著者(相続専門税理士)、ライター(相続税担当の元国税専門官)、編集者(相続のド素人)の3者による対話形式なので、スラスラ読めて、どんどん分かる! 【親は】子に迷惑をかけたくなければ読んでみてください。【子どもは】親が元気なうちに読んでみてください。本書で紹介する5つのポイントを押さえておけば、相続は10割解決します。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
生前贈与による節税の落とし穴
生前贈与による相続税対策をするときは、やり過ぎは禁物です。
相続税の負担が減る代わりに、のこされた相続人がモメる可能性があるからです。
「特例の活用」で税は減っても
きょうだい間で火種に
たとえば、相続人が長男と長女の2人というケースで、長男が家を建てるために親から1000万円の生前贈与を受けたとしましょう。このときに「住宅取得等資金贈与の特例」を活用すれば、長男に贈与税はかかりません。
そして、親の1000万円が子どもに移った分、親が亡くなったときの相続税を節税できます。でも、そのことを長女が知れば、「なんでお兄ちゃんだけ1000万円もらうの!? ズルい!」と反発することは容易に想像がつきます。
いずれ相続が起きたとき、長女は「今度は私が多くもらいたい」と思うでしょうし、長男は「生前贈与と相続は別物だから、相続は半々で分けるべきだ」と主張するかもしれません。
このようにして、生前贈与をきっかけに家族がモメてしまうわけです。
黙って贈与してもいつかバレる
贈与は、法律上では、あげる人ともらう人の合意で成立するので、ほかの家族に知らせずに生前贈与をすること自体は可能です。そのため、先ほどのケースであれば、1000万円の贈与をしたことを長女に黙っておけばトラブルは起きないと思うかもしれません。
しかし、それは残念ながら甘い考えなのです。相続がはじまると、同居をしていなかった相続人から「親の通帳を見たい」と言われることがよくあります。ここで通帳を見せないと怪しまれますから、渋々ながらも通帳を見せることになるでしょう。
このときに、「お父さんの通帳から大きなお金が出ている」「そういえばこの時期にお兄ちゃんが家を建てた」となると、贈与があったことは簡単にバレてしまいます。たとえ通帳を捨てても、相続人なら金融機関から被相続人の預金口座の明細をとり寄せることも可能ですから、あとから生前贈与の事実が明らかになってしまうのです。
「節税できるからやるべき」とは限らない
昨今は生前贈与を使った相続税対策の話題がメディアなどに多く出ていて、いろいろなところですすめられています。ただ、現実に落とし込んで考えると、相続税対策になるとしても「実際はやるべきではない」というケースが少なくないのです。
そもそも相続税がかからない家庭であれば、相続税対策をする必要はないのですから、ただ単に家族同士が争うきっかけをつくるだけになる可能性もあります。
あげる側の老後資金にも要注意
さらには、「贈与をする人の生活におよぶ影響」を多くの人が見落としているようにも感じます。たしかに、生前贈与を年間110万円までに収めればもらった人に贈与税はかからず、これを何年も続けると、数千万円を無税で相続人に渡すことができます。
しかし、それだけのお金を生前贈与したら、あげる人の生活に影響が出てきます。親がお金を贈与しすぎて老後の生活資金が尽きてしまい、不安を抱えながら生活を送らなくてはならないとしたら、それは問題です。
最も大事なのは家族との話し合い
このような生前贈与の問題を避けるには、お金をあげたあとの影響をきちんと事前に考える必要があります。相続税の節税だけに目を向けるのではなく、贈与する人や、贈与を受ける人、さらには贈与を受けられない人におよぶ影響を考えるのです。
あとから問題が起きないようにするには、家族でしっかり話し合いをすることが欠かせません。生前贈与をすることで、むしろ家族同士の関係がよくなり、しかも相続税対策になるような、理想的な形を目指してください。
※本稿は、『相続のめんどくさいが全部なくなる本』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。
![【節税したい人必見】「生前贈与」で損する人・得する人の決定的な違い[贈与税の特例一覧付き]](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/b/c/360wm/img_bca638124ebde6f896528f5460cb645c98692.jpg)