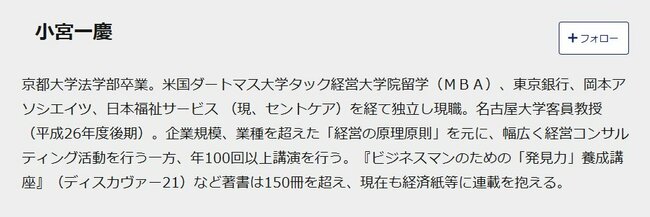その後、3代目社長は本当にAさんを常務に昇進させて重要な仕事を任せたり、折々に相談を持ちかけたりしました。そしてAさんも、3代目社長の期待に応えようと、態度を変えてがむしゃらに働きました。それは経営層の軋轢(あつれき)を心配していた社員や取引先が驚くほどでした。
経営コンサルタントの大先輩・一倉定先生は、「人の心」の何たるかを非常によく分かっていて、「経営は心理学」とも表現されています。3代目社長も、「人の心」の何たるかを理解していたのでしょう。
下積みの修業を
おろそかにしない
反対に、人の心を蔑ろにして失敗してしまった例もあります。
ある優良中小企業の社長は息子を後継者にしようと考え、30歳くらいで取締役に昇進させました。肩書上は、ほとんどの社員が年上部下になったわけです。
すると、息子は実力が伴わないのに肩書をひけらかして偉そうな態度をとるようになりました。社長は何度も諭したのですが、息子は聞く耳を持ちません。ついに、後継者にすることを諦めてしかるべき退職金を払って追い出してしまったといいます。
この失敗から学べることは、後継者だからといって、下積みの修業をおろそかにしてはいけないということ。できれば他社で働かせて“他人の飯を食う”経験をさせ、自分の会社の常識は他社の非常識であることを学ぶことも重要でしょう。自社に入社した後も、しばらくは一般社員と同じ立場で働かせるべきです。
そうすれば、将来後継者として年上部下を持っても、「人の心」の何たるかを忘れることはないでしょう。