住宅事情が許さないこともあるし、そうではなくても祖父母と同居するのは煩わしいという若い人も多いけれど、いい面がたくさんあるのです。また、老いた人といっしょに住み、やがて亡くなるのを見届けることも子どもにとって、とても大切な経験になります。
離れていると、いざ病気になっても小さな子どもは病院にお見舞いにもなかなか連れていけません。人の老いや死を、家族とともに見届ける経験は、つらいことですが大切なことのひとつでもあります。
エリク・ホーンブルガー・エリクソン(1902~1994年)もまた、私が尊敬する心理学者・精神分析学者です。
「アイデンティティ」(自己同一性)という概念は、エリクソンが初めて使いました。
アイデンティティとは、人間が青年期への成長過程で「自分とはなにものか」「いかに生きるべきか」を模索することによって、「これが自分である」といった感覚を持つこと、と言っていいでしょう。「これが自分だ」「こういう生き方をするのが自分の本来の姿だ」と自覚する、という概念です。
エリクソンは医師ではありませんが、精神分析家として問題行動を起こす多くの青年たちの心理療法を行いました。その後は発達心理学者として活動し、幼児期から老年期までの心理の研究をつづけた人ですが、彼は人間関係について、こう言っています。
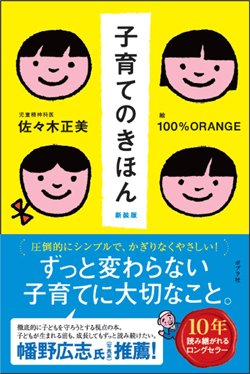 『子育てのきほん』(ポプラ社)
『子育てのきほん』(ポプラ社)佐々木正美 著
「倫理というものは世代間のなかで新しく生まれ変わり、そして次の世代に引き継がれるようにして、伝達されていく。だから世代間の関係が薄れた社会になればなるほど、倫理は失われていく」
同世代だけの関係ではなく、違う世代との人間関係がたくさんある社会は、倫理が伝達・再生されている社会であるということです。
人に迷惑をかけない、社会のルールを守る、相手を思いやり、思いやられることで生きていく、という生き方もまた、世代間の交流のなかで自然に教えられ、伝えられていくものなのではないでしょうか。
世代が違う人が「親」だけであってはいけないのです。







