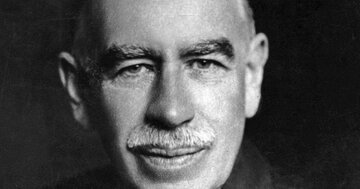不正も横行して強まった
「バブルを退治せよ」の声
バブル景気を経験した世代の人からは「あの頃は良かった」との回想をよく聞くが、国民の多くがバブルを謳歌していたわけではない。
地価と株価の上昇に眉をひそめる人も多かった。多くの資産を持つ人ほどバブルの恩恵を受ける傾向が強かったためである。
バブル膨張によって生まれたキャピタルゲイン(編集部注/株式や債券等、保有している資産を売却することによって得られる売買差益のこと)のうち約6割は高所得層に集中し、最も所得が低い階層は2〜4%にとどまったとの試算もある。
地価上昇によるキャピタルゲインも東京、大阪、名古屋の三大都市圏に集中し、地方との差が開いた。
労働者の賃金は上昇し、消費は活発になったが、住宅価格がそれ以上に高騰し、東京への通勤圏での住宅価格は「年収の5倍程度」から「7〜8倍程度」に上昇した。首都圏などに土地を所有している人はますます有利になる傾向が強まり、国民から不満の声が出るようになった。
庶民感覚とはかけ離れた土地・株取引、特別背任、贈収賄や不正取引など法に触れる不祥事や事件が相次いだことも、バブル景気の印象を悪くした。
国民の多くは好況を実感しつつも、持てる者と持たざる者との格差拡大、持てる者の倫理にもとる行動に怒り、「バブルを潰せ」、「バブルを退治せよ」という声が強まった。
バブル崩壊でやってきた
低成長の「失われた30年」
戦後の日本経済の歴史の中で、高度成長期とバブル期は二大黄金時代といえるだろう。日本経済の規模が急速に拡大し、国民の生活は豊かになった。
しかし、国民は急成長を手放しで喜んだり、浮かれたりしていたのではなく、高度成長期の末期には「くたばれGNP」、バブル末期には「バブル退治」という言葉が流行した。景気拡大や経済成長の恩恵を受けつつも、負の側面に目を向ける人が多かったのである。
バブル景気の過熱を警戒した政府・日銀は金融の引き締めや土地取引の規制に乗り出し、1990年代初頭にバブル経済は崩壊した。
その後、日本経済は「失われた20年」と呼ばれる停滞期に入る。失われた20年が過ぎてもなお日本経済は停滞しているとの意味を込めて「失われた30年」と呼ぶ人もいる。