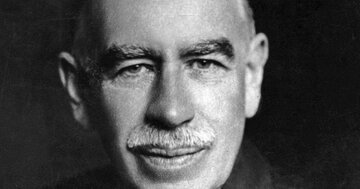日本の実質成長率の推移を見よう。高度成長期は約10%、1970〜80年代の安定成長期は約5%、90年代は約1.5%、2000年代は約0.6%と低下傾向が続いた。2010年代は約1%と少し盛り返したが、「失われた30年」は、ほぼ経済が成長していない状況だと説明する経済学者もいる。
働く人が減れば
成長は鈍化する
なぜ、成長率が急低下したのか。成長会計の手法を使って供給側の要因を探ってみよう。
90年代以降、資本(設備)、労働、技術進歩(編集部注/経済学では、技術進歩や生産の効率化など「質の向上」をもたら成長要因を「全要素生産性」Total Factor Productivity=TFPと呼ぶ。筆者は「技術進歩」をTFPの意味で使っている)の三要素のうち、労働の寄与度がマイナスに転じたのが大きな変化である。
生産年齢人口(15〜64歳)は1995年にピーク(8716万人)、労働力人口(就業者と完全失業者の合計)は1998年にピーク(6793万人)を記録し、減少に転じた。
働く人が減れば、成長は鈍化する。企業の設備投資は90年代以降も一定の貢献をしているが、成長率全体を押し上げるほどの勢いはない。技術進歩の貢献度も低い。
三要素のすべてに影響を与えているのは企業である。90年代以降、日本企業の行動が大きく変化し、成長率の低下につながっている。
バブル崩壊後、企業は設備、雇用、債務の「3つの過剰」を抱え込んだ。資金の出し手である金融機関にとって回収が困難な不良債権が膨らみ、経済全体の足を引っ張った。
企業は新たな設備投資を抑制しながら既存の設備や人員を整理し、財務内容の改善に取り組んだ。金融機関は経営統合や不良債権の処理に努めた。90年代以降、非正規雇用の労働者の割合を高め、人件費を削減した。
3つの過剰の整理や不良債権の処理にめどがついた2000年代初頭に景気はようやく回復軌道に乗ったのである。
「いざなみ景気」では
給料が倍になるまで41年
2002年2月から 08年2月まで戦後最長の73カ月にのぼった「いざなみ景気」が到来する。「景気回復の実感がない」という表現が普及したのはこの時期だ。この間の実質成長率は平均1.7%。高度成長期の「いざなぎ景気」(平均11.5%)、バブル景気(平均5.6%)に比べると明らかに見劣りする。