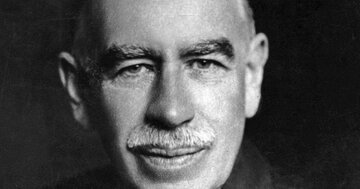今度は需要の面から経済成長への貢献(寄与率)を確認してみよう(需要を構成する各要素の経済成長率への寄与度÷経済成長率)×100(%)で算出する。「いざなぎ景気」では消費が51%、設備投資が25%。「バブル景気」では消費が45%、設備投資が35%。「いざなみ景気」では消費が37%、設備投資が27%、外需(輸出–輸入)が34%を占めた。
高度成長期とバブル期は国内需要が景気をけん引したが、いざなみ景気を引っ張ったのは輸出だ。とりわけ急成長を遂げた中国向け輸出の伸びが大きかった。国内で生み出したモノを海外に輸出すれば経済は成長する。しかし、そのモノを使うのは海外の人たちである。
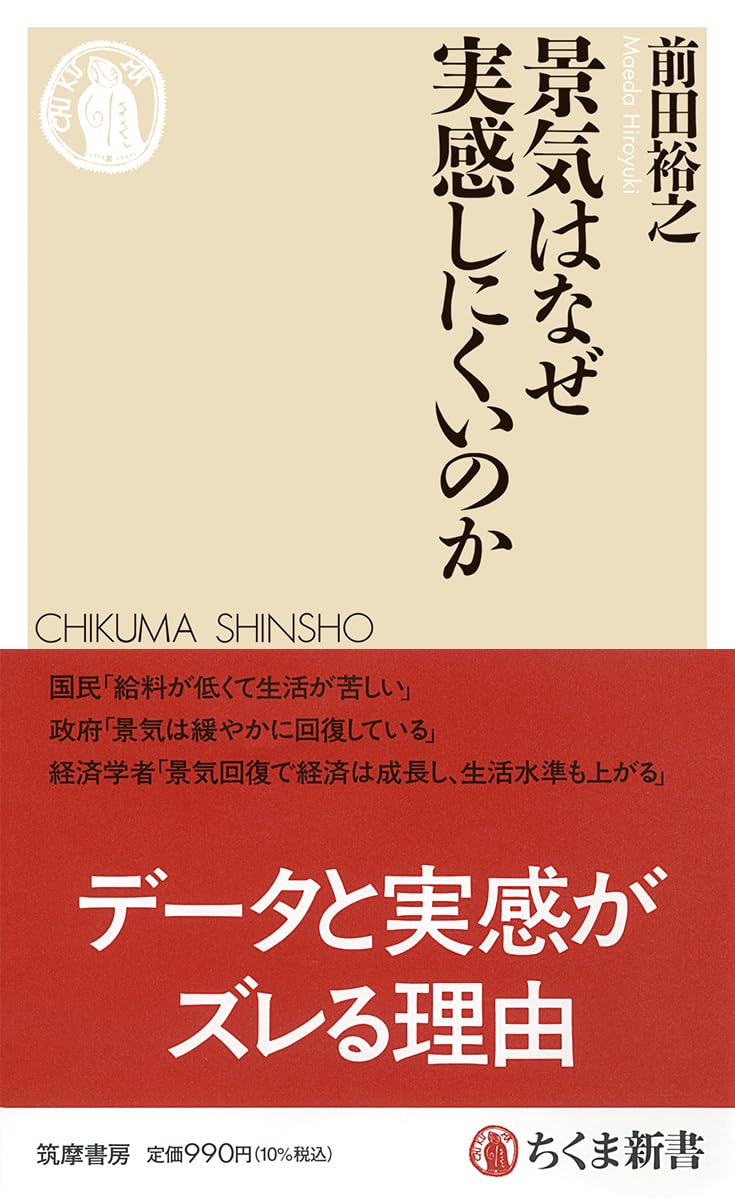 『景気はなぜ実感しにくいのか』(前田裕之、ちくま新書)
『景気はなぜ実感しにくいのか』(前田裕之、ちくま新書)
成長率が低いうえに、輸出のウエイトが高いとなれば、目の前の風景が変わり、生活が日増しに豊かになると実感する人がいないのは当然かもしれない。
ただ、成長率の低さを強調しすぎるのは問題だと筆者は考えている。経済活動の水準が低下しているわけではないからだ。
経済成長理論には「ルール・オブ70」と呼ばれる法則がある。70÷成長率を計算すれば、所得が2倍になる年数が大まかに分かる。
仮に成長率が10%なら7年で所得は2倍になる。高度成長期には実際にこうした現象が起きた。「いざなみ景気」の平均1.7%を当てはめると41年である。仮に2%なら35年、1%なら70年となる。
高度成長期やバブル期に比べれば「低成長」ではあるが、0.5%の成長でも影響は大きい。「低成長だから仕方がない」という言葉を国や企業が都合よく使っていないか注意が必要だ。