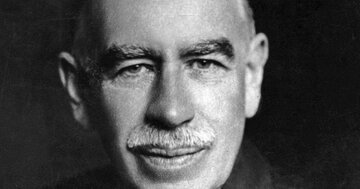戦後の日本は、風船を巨大にしてきた。前の年に比べて1%膨らませ方を抑制するだけでも大きな影響が出る。
風船を膨らませている人たちに均等に影響が及ぶのではなく、雇用保障がない弱い立場の人たちに真っ先にしわ寄せが来る傾向が強いのである。
政府が描く今後10年の
実質成長率は「2%程度」
政府はどんな未来を描いているのか。内閣府は2024年1月、今後10年程度(2024〜33年度)の経済展望を発表した。
技術進歩率が回復し、女性や高齢者などの労働参加が進むと仮定する「成長実現ケース」の場合で実質成長率は2%程度、名目成長率は3%程度、現在の傾向が続くと仮定する「ベースラインケース」では実質、名目ともに0%台半ばで推移すると見込んでいる。
同年4月には2060年度までの長期試算も発表した。2025〜60年度平均の実質成長率は、最も厳しい「現状投影シナリオ」で0.2%程度、最も楽観的な「成長実現シナリオ」で1.7%程度と推計している。同年6月に発表した「経済財政運営の指針」(骨太方針)では、実質成長率1%超を2030年度以降の目標として示した。
日本とアメリカの労働生産性(労働者1人が生み出している付加価値の額)を比べると、製造業、サービス業など広範な分野で日本の生産性は低い。日本が低成長を続けているのは、生産性が低いためであり、アメリカを手本に生産性を高めよと指摘する経済学者は多い。
日本企業はもっとイノベーションを起こせ、外国から優秀な人材を受け入れよう、女性や高齢者の労働参加率を高めよう……。経済成長を促すための様々な提案に耳を傾ける価値は大いにあるが、即効薬や魔法の杖はない。
成長会計による分析から明らかなように、日本経済が今後、安定成長期に匹敵する成長軌道に戻る可能性はほとんどない。精一杯、成長する努力を続けても、今後10年間の実質成長率が平均2%に届く未来は見えない。
アベノミクス景気での
賃金上昇はたった一度だけ
1%前後の成長を前提(目標)に、より多くの国民が景気回復や豊かさを実感できる経済構造にするために何をなすべきかを考えるのがより現実的ではないだろうか。
日本企業の行動が日本の経済成長には必ずしも貢献していない点も改めて確認しておきたい。国内の「3つの過剰」(編集部注/バブル崩壊後、企業が抱えた設備、雇用、債務のこと)の整理にめどがついた2000年代に入っても日本企業は人件費抑制の手を緩めず、非正規雇用の割合は4割近くに達している。