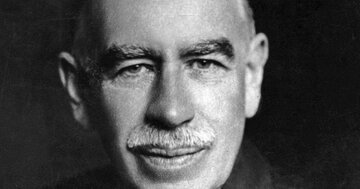2023年度決算で過去最高益を記録した企業の売り上げや利益を見ると、海外事業に依存している企業が極めて多い。経営者からは企業の経営戦略として海外事業に注力するのは当然という声も聞こえてくる。
円安で海外向け輸出(ドルベース)の円換算額が増えたり、海外拠点の売り上げが伸びたりすれば、海外事業をさらに拡大しようとする可能性が高い。海外事業が好調であれば、現地での設備投資を増やすだろう。海外での収益を国内で働く従業員の賃金の原資にはしづらいのかもしれない。
しかし、現状を放置していたら、景気回復も過去最高益の恩恵も実感できない人が増えるだけだ。
データを確認できる1971年以降で従業員30人以上の事業所(全産業)の実質賃金(物価変動の影響を除いた賃金)の前年比増減率の推移を見ると、「列島改造景気」の時期に該当する1972〜73年は8.4〜11.1%に達した。「バブル景気」の1987〜90年は1.6〜2.9%である。
「いざなみ景気」の2002年〜07年では、最低がマイナス1.8%、最高が1.5%。6年間のうちマイナスの年が3回だ。「アベノミクス景気」の2013〜18年では、最低がマイナス2.2%、最高が1.3%。6年間のうちプラスになった年は1回だけである。
低所得層の「貧困化」が
日本の格差拡大の特徴
一橋大学教授の森口千晶は、所得格差の視点から日本社会の長期的な変遷をたどりつつ、雇用や社会保障制度の問題点について論じている。
「景気」や「経済成長」に関する論考ではないが、「景気回復を実感できない国民」を生む社会の構造が浮き彫りになっていると筆者はみており、ここで紹介しておきたい。
森口によると、日本では高度成長期に所得格差が縮小し、1960年代後半には「一億総中流」と呼ばれる意識が生まれた。
そして、安定成長期に「日本型平等社会」が完成した。平等主義の単位は個人ではなく「世帯」であり、「男性正社員モデル」が基本だった。
しかし、1980年代以降の構造変化により、日本型平等社会の前提条件が揺らぎ始めた。少子高齢化の進行と世帯規模の縮小である。高齢者のみの世帯が増え、所得格差が広がる要因になっている。
さらに、1990年代以降の長期不況の影響で、既存の制度には包摂されない社会の構成員(高齢単独世帯、母子世帯、非正規世帯、無業世帯など)が増え、相対的貧困率が上昇した。
近年の日本における格差拡大の特徴は「富裕層の富裕化」を伴わない「低所得層の貧困化」にあると総括する。森口によれば、「日本型平等主義に内在していた格差が顕在化し、結果的に格差の広がった社会になった。」