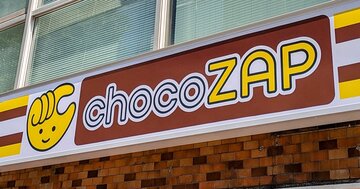写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
GWが明け、5月中旬は日本企業の決算発表が集中するシーズン。ウチの会社は大丈夫なのか――。それを調べる方法を、グロービス経営大学院教授の佐伯良隆氏が解説します(佐伯良隆著『決算書「分析」超入門2025』から抜粋・編集)。
* * *
信用を失った会社は事業を継続できない
安全性分析とは、ずばり「会社が今後も事業を継続していけるか」を確かめること。事業が継続できなくなるのは、会社が生存不能になるとき、つまり「倒産」です。
安全性分析のキモは、会社がこの倒産のリスクを抱えていないかを読み取ることにあります。
では、そもそも会社はどんな場合に倒産するのでしょうか。一般的には、「赤字が何年も続くと倒産する」というイメージがあるかもしれません。
もちろん、赤字が長く続けば倒産のリスク大ですが、厳密には「資金繰りに行き詰まったとき」に会社は倒産します。
資金繰りに行き詰まるとは、業績不振などで「借りていたお金を期日までに返せなくなる(債務不履行に陥る)」ことです。
手元の資金が枯渇して、「不渡りを出す(手形や小切手の支払いが滞る)」と、すべての金融機関にその事実が通告され、今後の融資が受けにくくなってしまいます。人に例えるなら、出血している重症患者が輸血を受けられないのと同じで、大変危険な状態です。
そして借入金を期限内に返済できず、返済猶予や追加融資にも応じてもらえなかった場合、会社は債務不履行状態となり、破産を申請することになります。
安全性は、会社の体つきと血液の流れをみる
では具体的に、決算書のどこをみれば会社の安全性がわかるのでしょうか。3章の収益性の分析では、損益計算書を主に使いましたが、安全性を分析するときは、貸借対照表とキャッシュ・フロー計算書の2表を使います。
人間と同じで、健康かどうかを知るには、体の内部(脂肪・筋肉・骨格の状態)や、血液の流れをみることが欠かせません。つまり会社の資産がどのように構成されているのか、また現金の動きに異常はないかを確認するのが、安全性分析なのです。