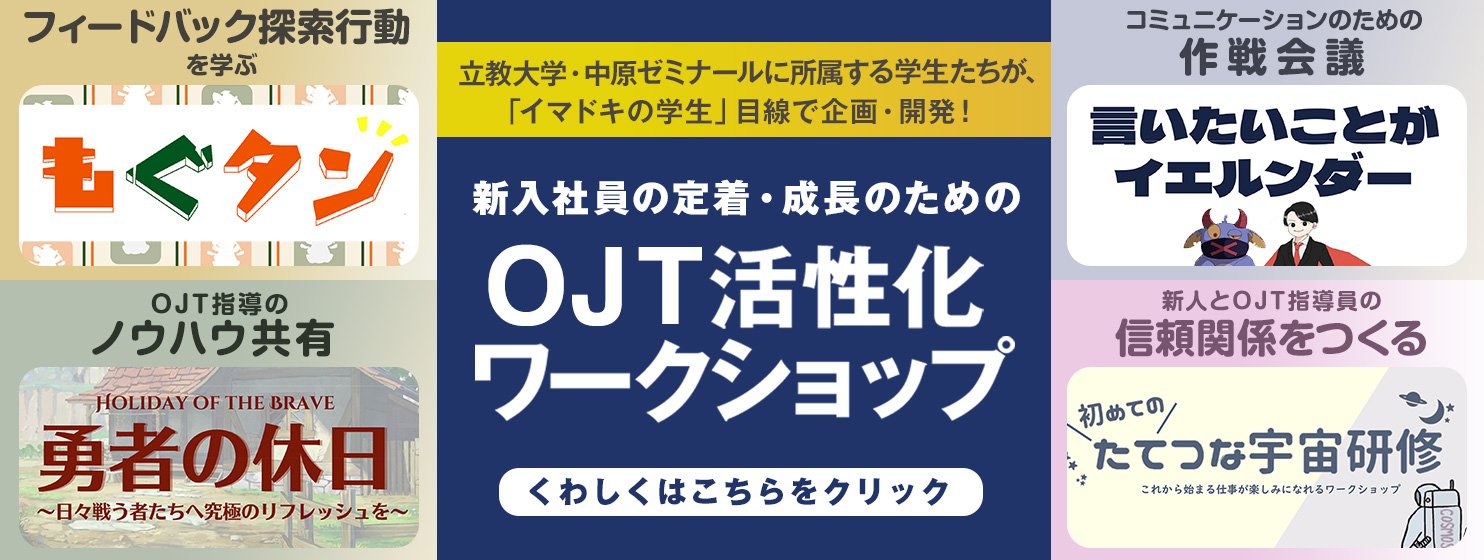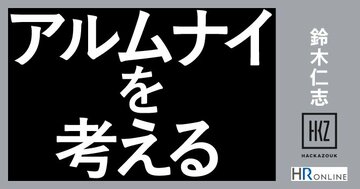面接における候補者のジャッジはAI、
リテンションは人が行うもの
話は少し寄り道しますが、先日、安野たかひろ氏をお招きして「『生成AI・DX』がもたらすエンジニア採用の未来」というセミナーを開催しました。採用業務を行うみなさんが気になっているであろう「人間と(生成)AIの棲み分けがどうなっていくか」という話題についてディスカッションしました。安野氏の見解は、リテンションは人が行うもの。ジャッジについては、現状は補助的な利用に留まるケースが多いが、近い将来にはAIが台頭するであろう、という内容でした。AIは大量のデータに基づいた客観的な評価や効率化に強みを発揮しますので、過去の採用データから内定者の特徴を学習し、判断の精度を高めることができます。面接官の主観や無意識の偏りを排除して、より公平な評価が可能になりますが、候補者の潜在的な能力、カルチャーフィット、熱意、コミュニケーションのニュアンスなどは、現時点のAIが完全に理解するには限界があると考えられます。最終的な判断には、面接官の経験、洞察力、人間的な相互理解が不可欠ですので、現時点では、「AIと人の協働」が現実的だと考えます。
選ばれる企業へ――
面接体験を起点とした採用戦略のアップデート
ここまで、アンケート調査に基づき、ITエンジニア・DX人材が選考体験で何を重視するのか、志望度を左右する面接のあり方、そして、その貴重な情報を採用広報へと繋げる重要性について解説してきました。候補者が、自身の技術力への理解や将来の成長機会、共に働く人々の質、企業の内情への深い理解を求めていることが明らかになりました。また、一方的な見極めではなく、技術的なディスカッションを通じた相互理解が、候補者のエンゲージメントを高めるうえで有効である点もお話しさせていただきました。
今後の採用活動において、面接は単なる評価の場ではなく、候補者の期待に応え、企業の魅力を最大限に伝えるコミュニケーションの場と捉えるべきでしょう。そして、そこで得られた「生の声」は、採用広報をアップデートし、より共感を呼ぶメッセージを発信する原動力となります。候補者のニーズを理解したうえでの採用戦略を立案し、実行していくことが、競争激化するITエンジニア・DX人材市場において、優秀な人材を獲得し続けるための鍵となるでしょう。