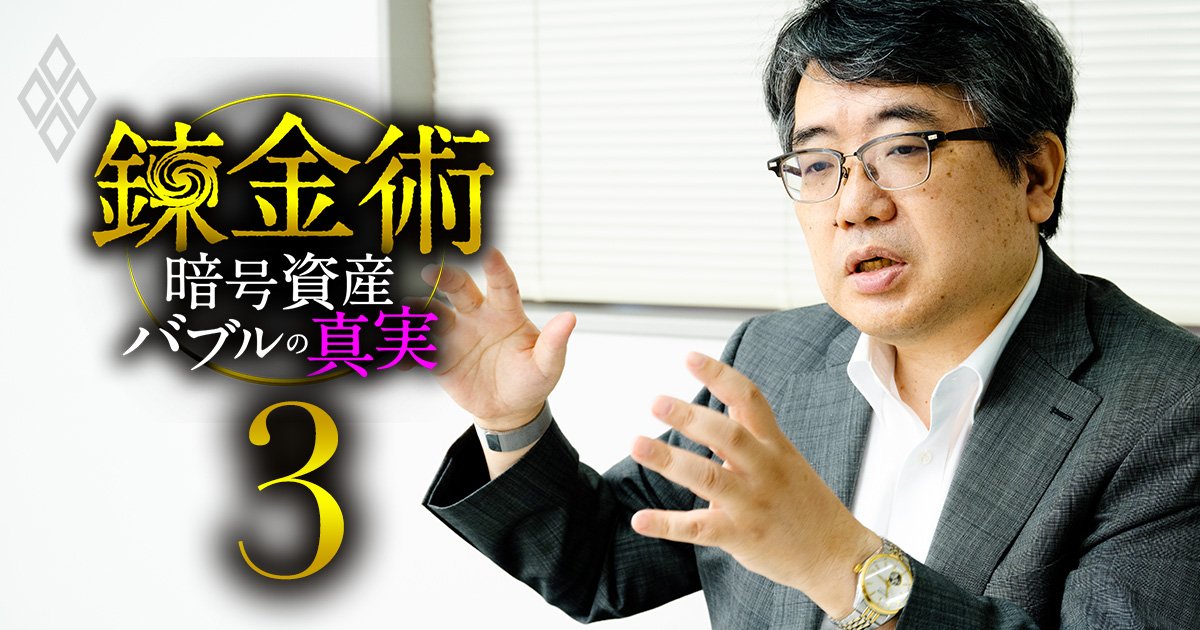 Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
金融庁の有識者会議で、暗号資産を株式などと同じ「金融商品」とする議論が進んでいる。現在の資金決済法から金融商品取引法(金商法)へ移管する案が有力視されるが、暗号資産の黎明期からその技術とリスクを研究してきた岩下直行・京都大学公共政策大学院教授は、そうした流れに強い懸念を表明する委員の一人だ。岩下教授が指摘する暗号資産の「不都合な真実」とは何か――。特集『錬金術 暗号資産バブルの真実』の#3で、インタビュー全文をお届けする。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 重石岳史)
ビットコインの価値は「誰も説明できない」
規制の出発点となった“誤解”とは?
――現在、金融庁のワーキンググループで暗号資産を金融商品取引法の対象とする議論が進んでいます。暗号資産の利用実態を踏まえ、金商法への移行に関する課題や懸念点をどのようにお考えでしょうか。
もともと暗号資産を何で規制するかは国によってもさまざまな考え方がありました。金商法での規制は、当初から「投機目的の商品なのだから金商法ではないか」という議論はあったのです。
ただ何が問題だったかというと、この正体がなんだか分からない。いまだに分かりません。「ビットコインって何ですか?」と聞いて答えられる人はほぼいない。「値上がりする」「デジタルゴールドだ」「匿名性がある」と言う人はいるかもしれませんが、ビットコインがなぜ価値を持つのかを、誰も説明できないのです。
株式は会社の持分権ですから、会社がもうかれば配当が入り、将来の解散価値も計算できます。しかし、暗号資産にはそれがない。実体が分からないものを法律で規制しなければならないので、規制する側も非常に苦労しました。
2017年に資金決済法で規制した際のコンセプトは、当時ビットコイン推進派が「仮想“通貨”」であり決済に使うと主張していたので、「では通貨ですね」ということで資金決済法で規制しましょう、となった経緯があります。
しかし、それから10年近くたちましたが、ビットコインが決済に使われている事例はほぼありません。その代わり、投機商品として値上がりした。なぜ値上がりするのかは買う人がいたから。なぜ買うのかといえば、値上がりするからです。
「ビットコインがなぜ価値を持つのか、誰も説明できない」
金融庁のワーキンググループでも厳しい指摘を続ける岩下教授は、暗号資産の価値の源泉が、麻薬売買やランサムウェア攻撃といった「犯罪利用」や「国家による金融規制の回避」という反社会的な実需にあると断言する。
岩下教授は、国内で相次ぐIEO(イニシャル・エクスチェンジ・オファリング、暗号資産を用いた資金調達)の全案件が公募価格を割り込む「全滅」状態である惨状を示し、これらを金融商品として制度化することは「過去に詐欺とされたスキームを追認するもの」であり、消費者被害を拡大させるだけだと警鐘を鳴らす。
金融商品化の先に待つのは、健全な市場か、それとも新たなバブルか――。投資家保護とイノベーションのはざまで揺れる日本の暗号資産規制の行方を、次ページに続く岩下教授へのインタビューから読み解く。







