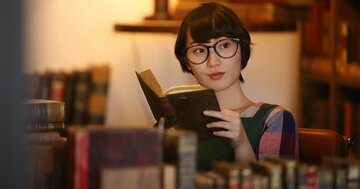そう考えると、江戸時代くらいまではそれぞれの地域における経済が潤沢に巡っていたのでしょうね。参勤交代で巨額の費用を使わされていたとはいえ、全国チェーンの店が地域に出張ってくることがほとんどなかったわけですから、地元産の商品やサービスを購入する機会が8割以上だったと考えられそうです。
明治維新によって誕生した政府は、こうした地域経済の強さを恐れたのかも知れません。諸藩が地域内経済循環を続けて豊かであり続けると、東京新政府の言うことを聞いてくれない。藩の経済力を低下させるためには、廃藩置県を断行するだけでなく、税を一旦すべて東京へと集め、大人しく言うことを聞く都道府県には手厚く再分配する。さらには、東京、横浜、大阪、神戸などの大都市に本社を置く中央財閥などを容認し、全国各地から貨幣を集める仕組みを増強させた。そんなふうに思えてきます。
道路はできてもなぜか
地元に金が残らなかった
コーンウォール地方は鳥取県と同じくらいの人口と面積らしいと書きました。ジェイン・ジェイコブズ(編集部注/作家、社会運動家)の『発展する地域、衰退する地域』の最後のほうに、「解説」として、かつて鳥取県知事だった片山善博さんの文章が掲載されています(注2)。片山さんは2000年代に「公共事業を減らす」という方針を打ち出した知事として有名です。
バブル経済が崩壊した後の1990年代は、各地の経済を立て直すために国が主導する公共事業を推進する都道府県が多かった時代です。公共事業は需要を創出し、さまざまな分野にその効果が波及し、雇用を増大させると言われていました。まさにケインズ的な発想ですね。ところが片山さんはこれを疑っていたのです。
(注2)ジェイン・ジェイコブズ著、中村達也訳『発展する地域衰退する地域』ちくま学芸文庫、2012、p393-405