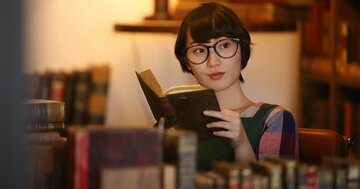例えば公共事業として道路を建設する場合、最初に土地を購入することになります。ところが、土地を所有者から購入しても、その代金で起業したり人を雇ったりする人はめったにいない。土地の所有者の多くは高齢者だからです。代金は老後の資金として貯金されるだけでしょう。
さらに、その高齢者が亡くなると、相続する子どもは東京や大阪に住んでいて、地元の預金口座の残高は大都市の人たちの資産に変わるだけです(注3)。
次に道路を建設するための機材と、セメントや鉄やアスファルトなどの資材が必要になりますが、これらを生産する企業は鳥取県内に1つもないそうです。したがって、これらを調達するための代金はすべて地域外に流出してしまい、県内への波及効果は望めない。貨幣が漏れただけなのです。
また、工法上の技術も地域外から調達することになります。橋梁やトンネルなどを建設するための高度な技術は概ねゼネコンに独占されているため、地元の工務店はその下請けにならざるをえない。土木作業員は地元の人が担うことになるでしょうが、下請けである地元の工務店で働く作業員の人件費は、道路建設の費用全体のうちの大きな割合を占めるわけではありません(注4)。
以上のように考えた片山さんは、鳥取県で公共事業を推進するのを止めて、ジェイコブズが提唱するような輸入置換を推進しようと決意したそうです。
地域外から仕入れているものを地域内で生産できるようにし、なるべく地域の貨幣を流出させないようにしたわけです。まさにコーンウォール地方で試算されたことを、同規模の鳥取県で実施してみたということになりますね(注5)。
地元の力で作りあげた
100年続く共同売店
輸入置換について考えるとき、思い浮かぶのが共同売店です。沖縄を中心に、周辺の離島にも広がった地域運営型売店です。ワークショップで「この地域にもコンビニが欲しい」という意見が出るたびに、「共同売店を経営してはどうですか?」と提案したりしています。