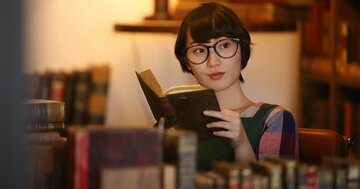写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
現在の無人販売所といえば、監視カメラやロッカー、QRコード決済で、防犯対策に奔走している。一方で、ある地域の販売所では、お金を盗まれてもあえて対策しないという選択がなされていた。その背景には、数字では測れないある想いがあったのだ。※本稿は、山崎 亮『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
余った野菜の行き場が
無人販売所になった
各地を歩いて、私が共同売店とともに興味を持っているのが「野菜の無人販売所」です。無人販売所については、誕生から歴史的変遷までをまとめた書籍が見当たらないため、どんなふうに生まれたのかを想像してみることにします(注1)。
ある人が畑で野菜を育てているとします。その人は収穫した野菜を出荷するために箱詰めしますが、大きく曲がっていて箱に入らない野菜やキズが付いた野菜などは出荷できません。あるいは、求められているよりも多くの野菜を収穫した日は、そのすべてを箱に詰めることはできません。
そうやって余った野菜は自宅で調理して食べるのですが、その数が多いと食べきれません。漬物などの保存食にしてもまだ余る場合、近所に住む親戚や友人に配ろうとするでしょう。顔が見える関係における「おすそ分け」ですね(1)。
ところが地域に住む人の多くが同じく農家であり、同じ季節には同じ野菜を収穫していて、同じように野菜を余らせている可能性が高い。農家ではない人を探して差し上げようとするのですが、その家にはすでに別の農家からのおすそ分けが届いている可能性も高い。
(注1)これは私の個人的な想像です。きっとこんな変遷だったんだろうなぁと思うことを書きますが、史実は違うかもしれません