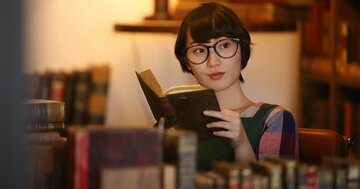写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「地方創生」という言葉が使われはじめて長いが、東京への一極集中はいまも止まらない。そんな中、地域経済を持続させるヒントとして注目されているのが「輸入置換」。外から買っていたモノを地元で作ることで、お金の流出を防ぐ考え方だ。実はこの輸入置換を、100年以上も前から実践している売店が沖縄にある。古ぼけた共同売店の経営から、私たちが学べることとは何か。※本稿は、山崎 亮『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(光文社)の一部を抜粋・編集したものです。
地元の商品を1%買うだけで
1万5000円も返ってくる?
『地元経済を創りなおす』(編集部注/枝廣淳子著、岩波書店)にも登場するイギリスのニュー・エコノミクス・ファンデーション(NEF)という研究機関が、コーンウォール地方を対象として試算した結果が興味深いものでした。
コーンウォール地方というのは、だいたい日本の鳥取県と同じくらいの面積と人口なのだそうです。この地方で暮らす人と、働く人と、訪れる人が、それぞれ1%だけ多く地元の商品やサービスを購入することにした場合、地元で使われる貨幣が年間で約75億円増えると試算されたそうなのです。
鳥取県と同じくらいの人口であれば約50万人ですから、1人あたり1万5000円の違いが生まれるということになります(注1)。あるいは、鳥取県の年間予算が約3000億円ですから、その2.5%分と考えることもできます。
地域で生活したり仕事したり観光したりする人たちが、わずか1%だけ多く地元産を選ぶことによって、これだけの経済効果があるということなのです。これが2%、あるいは3%増えるとしたら、地域を巡る貨幣は格段に増えることとなるでしょう。
(注1)全員が1%多く地元産を購入すれば、あなたの手元に巡る貨幣が1万5000円増える可能性が高まるという感じですかね