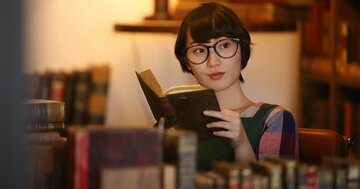客が本当に欲しいものを
売れば潰れることはない
そのうち、奥の人々の酒の消費量がとても多いことがわかってきたこともあり、自分たちで酒を醸造しようということになります。続いて茶葉も栽培しようということになります。そのため、地域内に酒造工場と製茶工場が建設されます。
また、山から切り出した木材を効率的に製材して輸出するため、製材工場も建設されました(注9)。こうした物品を運ぶため、奥共同店が所有する船は時代とともに大型化し、より多くの商品を出荷したり、日用品を仕入れたりするようになりました。
この間、奥共同店の経営は悪化したり回復したりを繰り返しています。常に順風満帆だったというわけではありません。
しかし、そのたびに地域住民がアイデアを出し合って、危機を乗り越えてきたのです。戦後は、この地域まで公道が通るようになり、ようやく船による運搬ではなく、トラックによる運搬が可能になります。地域住民の多くも自動車で移動するようになり、ガソリン需要が高まります。こうなると奥共同店は給油所も併設するようになります(注10)。
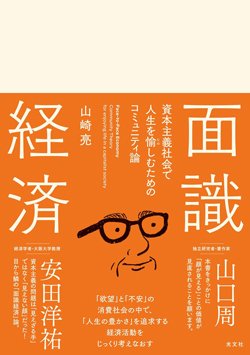 『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(山崎 亮、光文社)
『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(山崎 亮、光文社)
奥共同店の歴史からわかることは、地域住民がみんなで応援する店は繁盛するということです。地域の人々から必要とされる店であれば、100年続くことも可能だということです。
奥共同店は、紆余曲折があったとはいえ現在でも地域住民によって経営されています。もしワークショップで「うちのまちにもコンビニがあったら」という話が出たなら、その考え方を輸入置換して、自分たちでおしゃれな共同店をつくってみてはどうでしょう。そこで働く若者を応援してみてはどうでしょう。
まずはワークショップ参加者全員が応援することを約束し、各人が自分の友人や親戚にも共同店の価値を伝えるのです。説明のための小さな冊子をデザインしても良さそうです。ワークショップで話し合いながら冊子の内容を決めて、なぜこの地域に共同店が必要なのかを説明できる人を増やしていくのです。