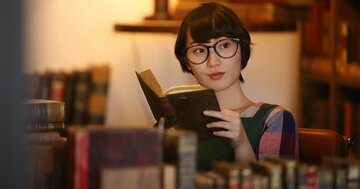沖縄で初めて共同売店を経営したのは、沖縄本島の最北端にある国頭村の奥という地域です。奥は、国頭村のなかでも最北端で、そこから先は海しかないという地域です。この地域に「奥共同店」が誕生したのは1906年のことです。すでに100年以上の歴史があるわけです。誕生の経緯は、『創立百周年記念誌』に詳述されています(注6)。
それによると、この地域には当初、雑貨商を営む人が2人いたそうです。1人はこの地域出身の人で、もう1人は外の地域から流れ着いてきた人でした。そのうち、外の地域からやってきた人が、自分の店で扱う商品を増やし、地域外で仕入れたものを住民に販売することで莫大な利益を得るようになってきたのです。
これに対して、何人かの地域住民が異を唱えます。地域外の出身者が、地域外から船で仕入れたものを地域住民に売って暴利を貪っている。自分たちの地域で独自の売店を作り、自分たちで経営したほうがいいのではないか。
こうした動きに、もうひとつの雑貨商を営んでいた地域出身者も呼応し、奥共同店が誕生したというのです。現在でいうコミュニティビジネスですね。『創立百周年記念誌』にも「奥共同店が近代資本主義的要素の侵入を契機として設置された事は、奥共同体の自己防衛の一策であった」と書かれています(注7)。
こうして誕生した奥共同店は、地域住民によって経営され、設立の際に地元銀行から借りた資金も3年以内に返済し、商品の運搬に使う「やんばる船」を3隻購入しました。
扱う商品は、地域住民が必要とするもので、酒、茶、煙草、醤油、塩、農具、日用品だったそうです。こうした商品は、地域外の都市で仕入れて船で運ばれてきました。また、地域住民が山から切り出してきた木材などを船に積んで、那覇などの都市部にて販売していました(注8)。