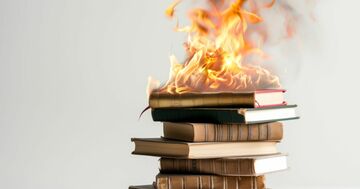東大には国粋主義と民本主義が同居していた Photo:PIXTA
東大には国粋主義と民本主義が同居していた Photo:PIXTA
「欧米文化の配電盤」と「天皇中心体制強化」
東京帝大にはなぜ二重性があったのか
大学の自由な言論を封殺する起点となった滝川事件や天皇機関説事件で、進歩的知識人らを激しく攻撃した国粋主義者・蓑田胸喜が、東京帝国大学に籍を置いていたことは単なる偶然とは言えない。
ジャーナリストの立花隆は、1998年2月から7年半、月刊誌『文藝春秋』に「私の東大論」を連載したが、最初の4回は『東大生はバカになったか』(文藝春秋、2001年)として出版された。「知的亡国論+現代教養論」のサブタイトルの通り、大学論であり、教養論である。
立花の問題意識は次第に「東大をのぞき窓に戦前の天皇制国家を考える」に変わり、5回目以降の連載は「天皇と東大 大日本帝国の生と死」(同、2005年)の書名で出版され、この中で蓑田を取り上げている。
立花は、近代国家として動き始めた明治初期の日本社会のスローガンは「和魂洋才」だが、「大学は『洋才』の輸入総代理店のおもむきを持っていた。『和魂』は洋才専門大学のカリキュラムにおさまらず、国史と国文学をのぞくと、事実上なきに等しかった。著しい不満を持っていたのが、右翼国粋主義者(復古主義者)だった。蓑田胸喜に代表される人たちの不満を爆発させたのが京大の滝川事件」と分析した。
洋才と和魂という2つの勢力がぶつかり合った舞台が、東京帝国大学だった。蓑田は、東京帝大に入学すると、憲法学者の上杉慎吉に師事し、上杉の指導する東京帝大の右翼運動の源流とされる興国同志会のメンバーとなった。上杉は天皇主権説を主張し、美濃部達吉らの天皇機関説と激しく論争をしていた。
当時、法学部では、大正デモクラシーの理論的支柱者、吉野作造の影響を受ける学生らによる新人会が勢いを持っていたが、軍事体制の強まりとともに両者の力は逆転していく。
立花は著書の中で、「天皇中心主義者(右翼国粋主義過激派)たちが、国体明徴運動に名を借りて、ほとんど無血クーデターを成しとげたかのごとくに、国政と社会体制と国民感情をほしいままに動かしていく体制が作られてしまった。軍部と結びつくことで、支那事変以後、国家総動員体制が作られていく。それが軍部主導のいわゆる日本型ファシズムである」と総括した。
蓑田はこうした時代や土壌の申し子であり、演出者だったのだ。