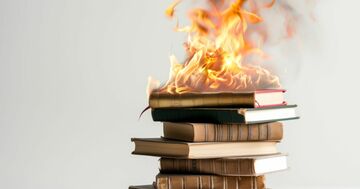1889年に制定された明治憲法は、天皇を主権者と定め、同時期に制定された皇室典範や教育勅語とともに天皇中心国家の支柱となった。帝国大学は、天皇国家を学問的に支える役割も担わされた。
一方で明治維新の日本にとっては、近代化、欧米文化の吸収の時代でもあった。作家の司馬遼太郎は、東京帝国大学を「欧米文化の配電盤」と位置付けた。海外の先進的な学問や技術を吸収し、日本全土に波及させる役割があった。世界の潮流から遅れた幕藩体制的な文化や風土を改革する使命があり、お雇い外国人を起点として新しい日本を作る狙いである。
こうした歴史から東京帝大は、西洋の学問を輸入する知的側面と官僚養成という統治面の「二義性」、欧米文化を吸収する先進的な性格と天皇中心の体制を強化する日本的で国家主義的な性格の「二重性」を持つことになったのだ。
学内を二分した思想潮流戦時体制で
国粋主義が凌駕
東京帝大の先進性を象徴する人物としては、大正デモクラシーの理論的指導者となった法学部教授の吉野作造が著名だ。欧米に3年間留学し、特にアメリカのプラグマティズムに影響を受けた。帰国後は政治史を担当し、『中央公論』を舞台に積極的な言論活動を展開した。
吉野の思想は、国民主権の民主主義とまではいかない。主権の所在はあえて問わず、万世一系の天皇の存在は認めるものの、国民の利益や福祉を最優先し、民意を尊重する「民本主義」だった。国民の声を政治に反映することを求め、普通選挙の実現や政党政治の推進を主張。政治だけでなく、労働運動や女性運動の発展にも影響を与えた。
美濃部達吉も大正デモクラシーの論客だった。恩師は、後に宮内大臣や枢密院議長などを務め、昭和天皇の側近となった一木喜徳郎だった。美濃部は文官高等試験に合格して内務省に勤務した後、欧州に留学し、東京帝大助教授になり、憲法や行政学を教えた。