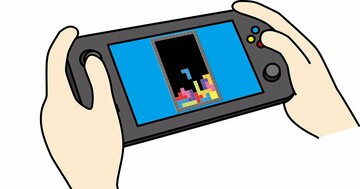曝露の2番目のメカニズムが「馴化」だ。これは特定の反応を引き起こす刺激を経験する回数が多くなるにつれ、その刺激がもたらす影響が弱まっていく現象である。大きな音を聞くと、本能的に飛び上がってしまうかもしれないが、同じ大きな音を何度も何度も聞くと、その反応は薄れていく。
危険を伴わない恐怖への曝露は
安全性の学習につながる
「消去」と「馴化」の違いを理解するために、誰でもステージに上がれる夜にライブハウスに行って、マイクの前でコメディを披露することへの恐怖を克服する場合を考えてみよう。この場合の「消去」とは、予想に反して、実際には辱めを受ける可能性はそれほど高くないと気づくことを意味する。
一方で「馴化」とは、何度もブーイングを受けてステージから降ろされた後で、コメディの披露中に失敗するのをそれほど気にしなくなることを意味する。
実際の危険を伴わない恐怖への曝露は、安全性の学習につながる。ただ曝露が恐怖を減少させる一方で、獲得された恐怖は学習された安全よりも持続性があることが示されている。
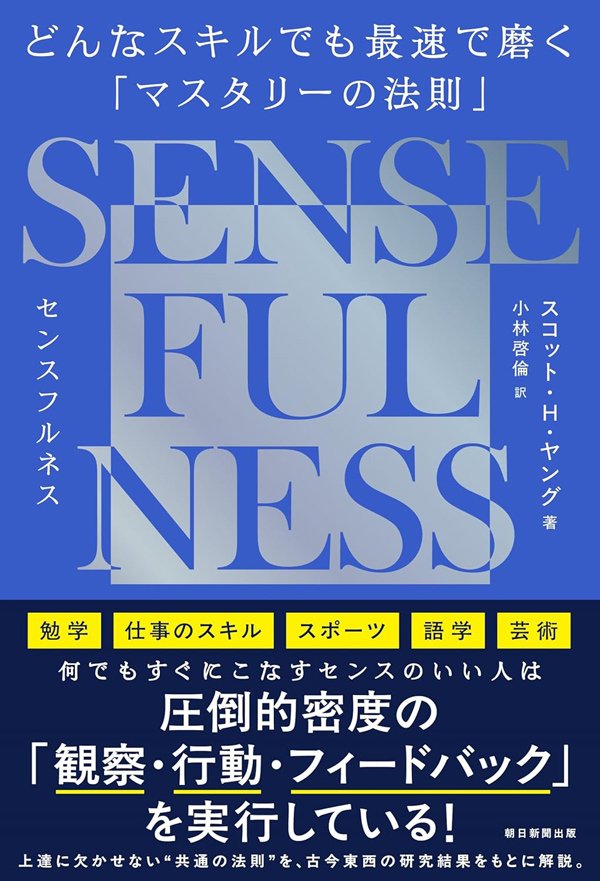 『SENSEFULNESS(センスフルネス) どんなスキルでも最速で磨く「マスタリーの法則」』(スコット・H・ヤング著、小林啓倫訳、朝日新聞出版)
『SENSEFULNESS(センスフルネス) どんなスキルでも最速で磨く「マスタリーの法則」』(スコット・H・ヤング著、小林啓倫訳、朝日新聞出版)
その結果、消去された恐怖が復活する場合がある。それは新しい状況で恐怖に直面したときや、曝露が行われる間隔があいたときだが、元の恐怖とはまったく関係のない一般的なストレス要因からですら、戻ってくることがあるのだ。
バーノンはこの理論に一致する現象として、空襲に対する恐怖が、爆撃を長期にわたって経験しなかった後でも、あたかも不安に対する予防接種の効果が部分的に失われたかのように、復活する傾向があることを観察した。
曝露は、さまざまな状況で提供され、また定期的に更新される場合に、より効果的に機能するのである。さらに一部の研究は、曝露中に時折恐れていた結果が発生するという「偶発的な強化」が、まったく危険がない曝露よりも持続的な効果をもたらすことを示唆している。
これは、偶発的に起きる不快な経験に対する安全性の学習がより強固なものとなるためである。