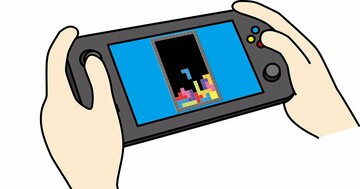心理学において、不安の起源は長きにわたり研究対象となってきた。
行動主義の父ジョン・ワトソンは、恐怖は単純な条件付けのプロセスから生じると論じた。彼は悪名高い「リトル・アルバート(アルバート坊や)実験」において、生後11ヵ月の幼児に白いネズミを見せながら、背後で鉄棒を叩いて大きな音を立てた。するとその幼児は、騒音の恐怖とネズミを結びつけ、ネズミだけでなくあらゆる白い毛皮のものに恐怖を抱くようになった。
この恐怖の条件付け理論は、第2次世界大戦中のロンドン大空襲における人々の反応の違いを説明するのに役立つ。
「ニアミス」を経験した人々、つまり爆撃された建物の中にいたり、致命傷を負った人を目撃したりした人々は、一時的に恐怖が蘇ることがよくあった。
非合理的な不安が続くのは
それを回避しようとするから
一方で「リモートミス」、つまり遠くで爆撃の轟音(ごうおん)を聞いただけで、自身に危害が及ばなかった人々には、恐怖が減少する傾向が見られた。恐怖にさらされたことでそれが悪化するのか、それとも軽減されるのかは、危険がどれほど直接的であったかなどに左右されるのである。
恐怖の条件付け理論は、恐怖がどのように発生するかについての明確な説明を提供するものではないが、私たちの不安を持続させる要因が何であるのかを考える上で有効な出発点を提供してくれる。
オーバル・マウラー(編集部注/米国の心理学者)の有力な二要因理論によれば、非合理的な不安が続くのは、私たちがそれを回避しようとするからだ。脅威を感じた場合、それを中和する方法を見つけようとするのが自然な反応である。
スピーチをすることに不安を感じる人は、職場でプレゼンを逃れるための言い訳を探そうとする。方程式に不安を感じる学生は、数学の授業を避けようとする。内向的で不安な人は、パーティーには来ず家にいる。しかし不安の対象から逃れることには、不安を根絶するのを難しくする2つの副作用がある。