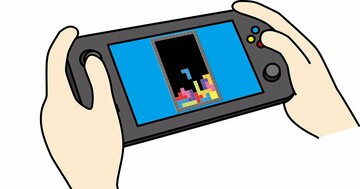第1の問題は、潜在的に危険な刺激を避けることによって、想像上の脅威が現実において重大であるかどうかを把握するための新しい情報を得られないという点だ。
フィードバックを避け続けていると、恐れを抱く刺激と危険との間に形成された、条件付けの関連性を消し去ることができない。琥珀(こはく)に閉じ込められた昆虫のように、私たちの恐怖は、それを否定する証拠に遭遇することができなくなるゆえに保存され続けてしまう。
不安との接触がもたらす
「消去」と「馴化」とは
第2の問題は、回避が自己強化されることだ。不安を感じる状況(たとえば試験やスピーチ、就職の面接など)を想像してみてほしい。それを心配することで、あなたは知覚された脅威を減らすために何らかの行動を取る(履修をやめる、別の人に発表してもらう、就職の機会を逃すなど)。今や不安はなくなり、あなたは安心する。
しかしこの安心感は心理的な報酬として作用し、将来の回避行動を強化してしまう可能性がある。このタイプの条件付けは、負の強化として知られている。潜在的な苦痛の除去が、中枢神経系に対するポジティブな信号として機能するからである。回避は不安を永続させるのだ。
曝露すなわち不安の対象にさらされることは、「消去」と「馴化」のプロセスを通じてその不安を和らげる。
「消去」という用語は、動物の学習に関する研究に由来する。ベルを鳴らして餌を与えると、犬はベルだけで唾液(だえき)を分泌することを学習する。しかし、餌を与えずにベルを何度も鳴らすと、最終的には学習された反応が消去される。同様に、恐怖の条件付け理論によれば、不安とは信号と危険の間の関連付けを学習した状態である。
危険を経験することなく信号に身をさらすことによって、私たちは自分の予想を修正する。その結果、元の恐怖学習が抑制されるのである。