そもそもうなぎミステリー
回遊魚と聞くと海の中を泳ぎ回っているマグロやカツオを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実はうなぎも回遊魚の仲間です。回遊魚の中にも異なる呼び名があります。川と海を行き来する魚を通し回遊魚、サケのように海で育って川で産卵する魚を遡河(そか)回遊魚、うなぎのように川で育って海で産卵する魚を降河(こうか)回遊魚といいます。ニホンウナギは、どこの海で産卵するのか長年の謎でした。2005年にやっと塚本勝巳名誉教授(東京大学大気海洋研究所)によって、マリアナ諸島西方海域と、判明しました。
産まれたばかりの赤ちゃんうなぎはレプトセファルスといって透明の細長い小さな木の葉のような形をしています。レプトセファルスは海流に乗って太平洋を北上しながらシラスウナギへと変態します。卵から孵って約半年後、中国や台湾、日本、韓国の河口に辿り着きます。
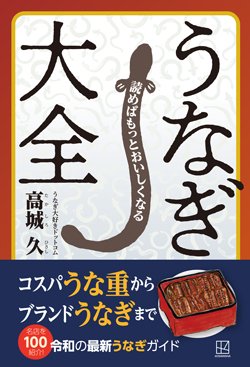 『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)
『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)高城 久 著
河口付近で漁師に捕られたシラスウナギは、養鰻場でおいしい養殖うなぎに育てられます。この関門を潜くぐり抜けたシラスウナギの八割は餌が豊富な河口付近で育ちます。河口付近の海で育ったうなぎを海うなぎ、河口付近の海水と川の水が混ざった場所で育ったうなぎを汽水うなぎと呼びます。
競走に敗れここを棲まいにできなかったうなぎは川を上のぼります。川で育ったうなぎを文字どおり川うなぎといいます。川は下流のほうが餌が豊富ですが、ライバルも多いのでさらに上流を目指すうなぎもいます。しかし、堰(せき)や水門という人間の造ったトラップが待ち受けています。
コンクリートではなく、土や岩ならばうなぎは登れることをご存じですか。水の中ではえら呼吸をしますが、身体のヌルヌルが乾くまでは皮膚呼吸ができるのです。だから滝だって登ります。鯉の滝登りの絵のようにゴウゴウと水が落下する瀑布(ばくふ)の中ではなく、滝脇の岩場をゆっくりと登ります。「うなぎ昇り」の語源は定かではありませんが、私は、滝口で岩場を登るうなぎを目撃した人が「うなぎ昇りだ」と言ったのが始まりだったのではないか、と思わずにいられません。
大人になったうなぎは成長の過程で、黄うなぎ、銀うなぎと名前を変えますが、生殖活動の詳細はわかっていません。うなぎは実は雌雄同体。産卵が近づいたうなぎだけが雌化します。それが、産卵のために川を下る下りうなぎ。大きく太く脂のりも抜群なので、漁師の格好の獲物ですが、ここで難を逃れたうなぎはまた大海原を2000kmもの旅をして産卵場所に向かいます。寿命は20年ともいわれ、体長1メートルを超えるものも。うなぎはとてもミステリアスで、まだまだ謎の多い生き物なのです。







