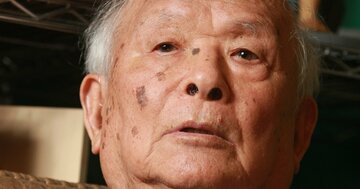写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
医師で作家の久坂部羊氏は、自ら死を選ぶ人たちの心の奥にある揺れや葛藤に長年向き合ってきた。命をめぐる決断の背後には、どんな“思い”があるのか。生と死のはざまにある繊細な心理を丁寧にひもといていく。※本稿は、久坂部羊『死が怖い人へ』(SBクリエイティブ)の一部を抜粋・編集したものです。
日常生活に支障をきたすほどの
「死恐怖症」という精神疾患
死の恐怖が高じて、日常生活に差し障るようになると、精神疾患と見なされて治療が必要となる。これを「死恐怖症(タナトフォビア)」と言う。「タナト」はギリシャ神話の死の神「タナトス」に由来し、「フォビア」は古代ギリシャ語で恐怖を意味する「ポボス」から来ている。
「死恐怖症」は、もともと繊細な人や神経質な人が、身近な人の死に接したり、事故や災害による大量死のニュース、リアリティのありすぎる映画やドラマなどで、死を強烈に感じたときに発症しやすい。
この状態になると、今すぐ死ぬわけでもないのに、死の恐怖が頭から離れず、ほかのことが手に付かなくなる。強い不安や不穏、不快感などで、心理状態が不安定な状態になり、身体的にも動悸(どうき)、発汗、口渇、震えなどが起こる。
私も子どものころ、夜に布団に入って死を考えると、そこはかとない不安に駆られて、叫びだしそうになるほど怖くなったが、たいていはそのまま眠ってしまうので、死恐怖症には至らなかった。
「死恐怖症」に似たものとして「死体恐怖症(ネクロフォビア)」がある。これは死体や死を連想させるもの(墓や葬儀や柩等)に極度の恐怖を抱くもので、「死恐怖症」と同様、日常生活に支障を来す。