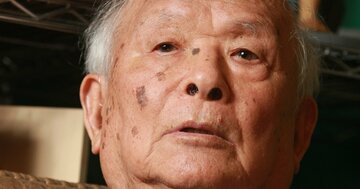日本のメディアは死体の映像を厳しく自粛していて、公共放送で鮮明に映し出されることはまずない。歴史的な写真等で死体が映る場合も、事前に警告が流されたりする。
人はどんなときに
死の恐怖を感じるのか
死体は一般に不快感を呼び起こすので、ことさら映し出す必要はないが、あまりに隠ぺいしすぎると、死体に対する免疫が獲得できず、何かのはずみで死体そのものや死体の画像や映像を見たとき、衝撃が大きくなる危険性がある。
死も死体も現実に存在するものなので、なかったことにするのではなく、少しずつ見せることが死や死体に対する耐性をつけることに役立つ。
虫や魚の死体→鳥や動物の死体→人間のきれいな死体(安らかに眠っているような)→人間の現実的な死体(事故や災害の被害者)→人間の悲惨な死体(事件や戦争の犠牲者)と順を追って、子どもから青年期あたりに、機会を捉えて見せておくとよいのではないか。
一部の死恐怖症の人を除き、四六時中ずっと死の恐怖を感じている人はいないだろう。
人はどんなときに死の恐怖を感じるのか。
多いのは、進行がんや重症化した新型コロナ肺炎など、死の危険性が高い病気の診断を受けたときだろう。突然、死が目の前に突きつけられ、たいていの人が驚愕(きょうがく)と動揺とともに恐怖に駆られる。
しかし、すべての人ではない。死の危険性の高い診断を受けても、比較的平然と受け止める人もいる。覚悟ができている人、運命を受け入れる心構えができている人、死の危険性が十分理解できない人、性格的に死の恐怖をあまり感じない人などである。
逆に、まだ死ぬと決まったわけではないのに、絶望して取り乱したり、自暴自棄になったりする人もいる。
医療者は専門知識があるので、ある程度、冷静に受け止められるが、一般の人は不安と疑心暗鬼に駆られ、悲観と楽観の間で揺れ動く。
しかし、これにも慣れの効果があり、がんが再発した人でも、最初はかなり落ち込むが、抗がん剤治療などを経て、2度、3度と再発の告知を受けているうちに、「またか」となって、あまり動揺しなくなる。そのうちに徐々に死への心づもりもできてきて、残り時間をうまく使って穏やかな最期を迎えるケースもある。