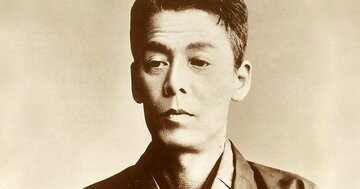金禄公債の額は家禄の5年から14年分で、元金は5年間の据えおき、6年目から毎年、抽選で支払う相手を選び、30年間で償還することになっていた。交付を受けた人数(華族、士族)は約31万3000余人、公債の総額は約1億7400万円、ひとりあたり平均で華族が6万4000円程度だったのに対し、士族はわずか500円足らずだった(当時の米価は1石=100升 約5円)。不平士族が出てきた背景にはこうした事情がある。
西南の役の後、政府が紙幣を乱発したためインフレになり、国民の生活が苦しくなっていた。特に士族は苦しく生活のために公債を額面よりも安く売り払って現金化した。額面100円の公債を半額で買いたたく商人もいたという。しかし、「商売は菩薩の業」と決めている初代忠兵衛は「必ず時価で買うこと」と部下に言い含め、時価の60円から70円で公債を買い取った。
松方正義のデフレ政策で
伊藤忠の同業者は死屍累々
その後、大蔵卿、松方正義の財政緊縮政策で物価は大暴落し、絹織物の卸値が3分の1となった。紅忠(伊藤忠の前身)の同業は損失を出し、倒産も数多く出た。しかし、初代忠兵衛は現金取引主義で信用販売を行っていなかったこともあって、不良債権を持たず、紅忠は微動だにしなかった。何より喜んだのは紅忠と現金で決済していた取引先だった。彼らもまた紅忠を真似て現金取引を主にしていた。初代忠兵衛の考え方が取引先を守ったと言える。
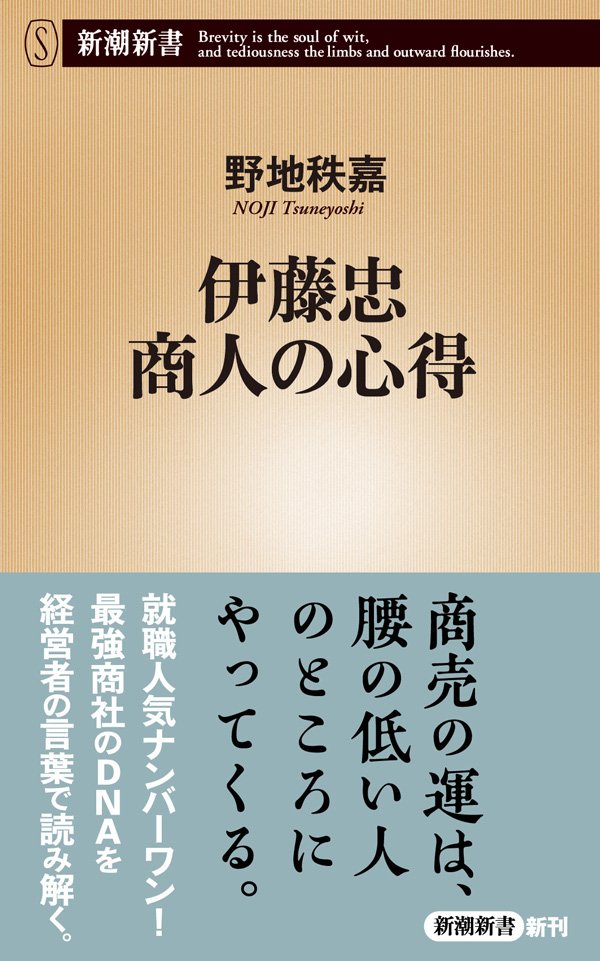 『伊藤忠 商人の心得』(野地秩嘉、新潮社)
『伊藤忠 商人の心得』(野地秩嘉、新潮社)
総合商社は今や投資会社になっている。株を持つ傘下の事業会社は数多い。仮に総合商社が先の見通しを誤ったら、事業会社にもまた影響が出る。さらには取引先も困る。
「商売は菩薩の業」を通すためには事業で失敗するわけにはいかない。先の見通しと商売に対する自信がなくては言えない言葉だ。