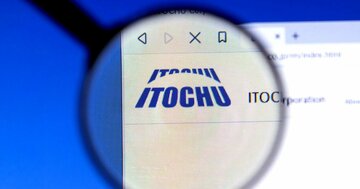野地秩嘉
三井は「米と漬物」なのに…伊藤忠創業者が全社員と「月6回のすき焼き会」を続けた理由
大手総合商社として知られる「伊藤忠」と「丸紅」。その原点となったのは、1858年に初代伊藤忠兵衛がおこした、小さなビジネスだ。幕府が倒れ明治の新時代を迎える激動期にあって、巧みに業容を拡大した経営手腕の背景には、近江商人の思想があった。※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』(新潮社)の一部を抜粋・編集したものです。

伊藤忠・岡藤正広会長が実践、“一流のセンス”が伝わる「ちょっとした手土産」の選び方とは
長らく業界の雄とたたえられた三菱商事と、昨今は熾烈なトップ争いを演じている伊藤忠商事。同社の躍進の立役者である岡藤正広会長のビジネス手腕は注目を集めているが、彼の仕事における大切な流儀のひとつに、手土産に関するこだわりがあるという。※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』(新潮社)の一部を抜粋・編集したものです。

「これを守れば商社マンとして大成功する」…伊藤忠・岡藤正広会長が断言する「たった4文字」とは?
かつて商社業界で万年4位に甘んじていた伊藤忠は、いまや三菱商事・三井物産のツートップを押しのけて時価総額首位にいる。この躍進の原動力となったのが、2010年以来同社のかじ取りを担う岡藤正広だ。経営者として圧倒的なビジネス手腕をふるう岡藤の、駆け出し時代の奮闘ぶりをたどる。※本稿は、野地秩嘉『伊藤忠 商人の心得』(新潮社)の一部を抜粋・編集したものです。

大学生の就職人気ナンバーワンの伊藤忠商事だが、岡藤正広会長が就活生や社員たちに最も求める「伊藤忠パーソン」としての資質はどういうものなのか。昨年12月に『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』を上梓した野地秩嘉氏が、岡藤会長に話を聞いた。

総合商社各社は2月3日、今年度第3四半期の業績とともに、今年度の連結業績見込みを発表した。資源価格の高騰や円安などの影響もあり、連結純利益で三菱商事が1兆1500億円、三井物産が1兆800億円と、総合商社で初の1兆円台を見込む。さらに伊藤忠商事も8000億円に達する見込みだ。総合商社で空前の好決算が続く中、昨年12月に『伊藤忠 財閥系を超えた最強商人』を上梓した野地秩嘉氏が、伊藤忠商事の岡藤正広会長に、同社の経営戦略や今年の経営環境などについて、話を聞いた。

岡藤正広は社長就任した翌年の2011年から初代伊藤忠兵衛の墓参りを欠かさない。墓所は京都の東山区にある大谷本廟だ。そこは浄土真宗本願寺派の本山、本願寺の墓地で、宗祖親鸞の御廟所(墓)がある。

2022年初めにマスコミ各社が出した「今年の展望」をあらためて見直すと、各メディアともに「新型コロナの感染がいつ収まるか」だけが論じる対象だった。2月下旬にロシアがウクライナに侵攻して、戦争になるとは日本ではどのメディアも予想はしていなかった。

岡藤正広の「防ぐ」経営思想がもっとも表れているのは、2014年から15年にかけて行った、タイと中国への巨額の投資だ。彼は当時、こんな説明をしている。「狙うべき地域は、人口が増え、マーケットが広がる中国を中心とするアジアです。そのためには現地の強力なパートナーがいると考え、CP、CITICとの資本提携を決めた。CPは東南アジア、中国での事業運営力がある。CITICは中国で知見と信用力があり、資金も持っている。財閥系商社が資源分野で強くなったのは電力会社などのお客と組んだから。伊藤忠はそれがない。その代わりに、生活消費関連でノウハウを持っている会社と組もうと考えた」

伊藤忠は2021年3月期の決算で時価総額、株価、連結純利益で総合商社のナンバーワンになった。だが、1年後にはロシアのウクライナ侵攻の影響もあり、資源価格が高騰。22年3月期の連結純利益トップは三菱商事、2位は三井物産となり、伊藤忠は3位となった。

総合商社の歴史と変化を簡単に振り返ると、政府の御用から始まった三菱商事、三井物産は国有財産の払い下げを受け、資源、エネルギーを主に扱う商社となっていった。三菱商事、三井物産であれば、鉄鉱石を輸入してきたら日本製鉄など製鉄会社が引き取ってくれる。石油、LNGを調達したら東京電力など電力会社が買ってくれた。当初から大口顧客がいたから資源商社と呼ばれる彼らの地位は盤石だった。他の領域の仕事もやっているけれど、今も資源を主として扱っている。

日本型のコンビニは、天才経営者鈴木敏文(セブン&アイ・ホールディングス名誉顧問)が作り出したものだ。おにぎりや弁当、総菜に注力したこと、宅配便の受付、公共料金の支払いサービスを始めたこと、そして銀行の設立。日本全国に約6万店ものコンビニが展開しているのは、鈴木のモデルを他社が模倣し、各地の消費者が受け入れたからだ。

東京・青山にある伊藤忠本社の8階には消費関連の部署が集まっている。2019年7月、そのフロアの一角に、未来の日本のためのカンパニー「第8カンパニー」が発足した。同社がカンパニー制へ移行した1997年以降、初めて設立された新しいセクションである。

伊藤忠が脱炭素社会に向け力を注いでいるセルロースファイバー、大豆ミートは、いずれも非資源分野のビジネスで、温室効果ガスの排出抑制につながる。セルロースファイバーは主に廃棄される木材を使う。大豆ミートは家畜の飼育に比べれば水の量を削減できるし、CO2とメタンの排出を抑制できる。

伊藤忠の食糧部門に所属する山田恵公はグループの食品素材メーカー、不二製油に出向し、PBFS(Plant-Based Food Solutions)事業部で働いている。担当しているのは大豆ミートなどのプラントベース(植物由来)フードの開発だ。不二製油には四つの事業分野がある。植物性油脂、業務用チョコレート、乳化・発酵素材、そして大豆加工素材だ。

岡藤正広が「浸透するまで繰り返す」としているのがマーケットインの考え方だ。プロダクトアウトとは正反対の考え方で、消費者が欲しいものを見つけてきて、提供することをいう。岡藤がマーケットインのシグニチャーとして挙げているのが「肌感覚の環境意識」から出発した事業だ。

伊藤忠が掲げる商いの3原則である「か(稼ぐ)・け(削る)・ふ(防ぐ)」で、削るよりも仕事が多岐にわたるのが「防ぐ」ことだ。伊藤忠には約270の関連会社があるが、岡藤正広とCFOの鉢村剛はそれらの会社と各社長の名前をすべてそらんじていて、主業務の概要も頭に入っている。

伊藤忠が目指す商人道を表す独特の標語が「か・け・ふ」だ。これもまた岡藤正広が考えた。同社の副社長でCFOの鉢村剛は初めて耳にした時、「か・け・ふ? それ、昔、阪神にいた掛布選手のことなのか」と妙な気がした。

第52回
2010年4月、岡藤正広は伊藤忠の戦後8代目の社長に就いた。その時の気持ちを後にこう思い出している。「4月某日、私は重い足取りで大阪から上京しました。それに先立つ2月11日、当時の小林社長から次期社長への就任を告げられていました。冷たい雨が降りしきる中、150年を超える歴史、連結60,000人以上の社員とその家族の生活を担う責任の重みを肩に感じたのを今でも鮮明に覚えています。それまで当社の歴代社長の多くは、東京本社の経営企画畑が就任しており、繊維カンパニーからの就任は実に36年ぶりのことでした。当時の足取りの重さは、東京から遠く離れ、規模も小さくなった大阪に本拠を置くカンパニー出身という、傍流意識のようなものがあったからかもしれません」(『統合レポート』)

第51回
小林栄三が力を注いだのはシステムインテグレーターとしてのCTCを確立したことだが、同時にITベンチャーへの投資もまた彼の守備範囲だった。なんといっても、IT、インターネットとそのビジネスについて理解していた幹部は彼ひとりだったからである。

第50回
92年に伊藤忠に入社して以来、IT、情報産業の最前線で走り回ってきたのが堀内真人だ。入社してから2年間はまだファックスとテレックスで仕事をしていたのが、94年に社内メールが始まり、95年には全面的に切り替わったことを覚えている。