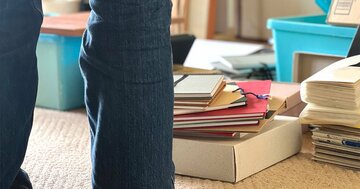実際、ほんとうに必要なものは、ほぼ決まっています。大枚はたいて購入した自宅の登記識別情報通知や健康保険証を「いる」「いらない」で悩むでしょうか。どんなに整理下手な人でも、一瞬で「いる」と判断できるはず。
迷うのは、なくても困らないグレーゾーンのモノばかり。つまり、迷った時点でそれはいらないモノなのです。
迷ったときは自分にこう問いかけてみてください。
「この『紙モノ』は、いざというとき、防災リュックに詰めて持ち出したい?」と。
ちょうどいい「紙モノ」の量はどれくらい?
人には、目に入らないモノは忘れてしまうという傾向があります。つまり、日常的に管理できるのは、パッと見渡せる範囲内にあるモノだけ。具体的には「両手を広げて届く範囲」です。
試しに実家に帰ったとき、チェックしてみてください。年老いた親は、自分の手の届く距離にしかモノを置いていませんから。裏を返せば、必要なモノは、両手を広げて届く範囲に収まる量で十分だということ。これを「両手の法則」と名づけています。
私は、片づけの講師として老人ホームを訪れる機会がありますが、高級感のあるレジデンスのようなところでも、大抵、部屋はワンルーム。収納家具も「両手の法則」に収まる大きさです。つまり、60歳を過ぎれば、暮らしにはそれで事足りるということ。ですから、「紙モノ」も、ワンルームに住むことをイメージして、両手を広げた範囲に収まるよう、できるだけコンパクトに。そして、取り出しやすい場所に置いておきましょう。
年をとれば、視力は落ちてきますし、体も思うように動かせなくなってきます。「大事だから」と、大切な書類を踏み台に乗らなければ取れない高い場所や、薄暗い床下にしまい込んでいる方がいますが、取ろうとして踏み外したり、かがんで腰を痛めてしまっては元も子もありませんよ。
命を守る!防災としての「紙モノ」整理
「紙モノ」を整理するのは、「自分に何かあったとき、家族が相続で困らないため」だけではありません。自身の命を守ることにもつながります。
もっともかさばって場所を取る「紙モノ」に、本や雑誌があります。かくいう私も、紙の本が大好きで、自宅にはたくさんの本が並んでいました。今も紙の本を読みますが、電子書籍を購入し、タブレットなどで楽しむことも増えました。きっかけは、東日本大震災でした。自宅にある本が、ほとんど床に崩れ落ちてしまったのです。こうなると、避難経路がふさがれてしまいますし、何より重たい本の下敷きになったら、命にも関わります。
高齢者ほど、「紙の本でないと読んだ気がしない」という人が多いのですが、年をとればとるほど、動作は鈍くなります。整理しておかないと、命に関わることを自覚しましょう。