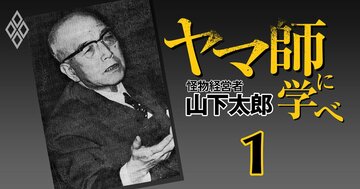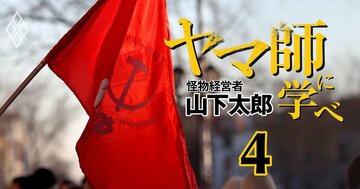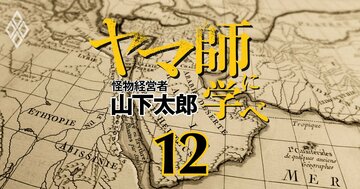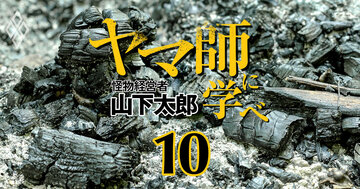Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
裸一貫から一代でトヨタ・松下・日立を超える高収益企業「アラビア石油」を作った破格の傑物、山下太郎──。太郎は、戦中の苦難を知る技術者・山内肇と共に石油開発に挑み、失われた命への責任感を胸に未来を切り拓いた。その戦争の記憶に基づく情熱は、日本の高度経済成長を支えた世代に共通するものだろう。現代においても経営者や起業家の原動力とは、「次世代のために何を残すか」という使命感であるべきではないか。この連載では、山下太郎の波乱万丈の生涯を描いたノンフィクション小説『ヤマ師』の印象的なシーンを取り上げ、彼の大胆な発想と行動力の核心に迫る。
高度経済成長を背負った世代の
情熱の根底にあった戦争の記憶
日本の高度経済成長を牽引した世代の多くは、戦争の記憶を心に刻んでいました。とりわけ、「二度と戦争を繰り返してはならない」という強い思いが、彼らの仕事への情熱や使命感の根底にあったことは見逃せません。山下太郎もまた、その一人でした。
太郎が石油開発の現場責任者として白羽の矢を立てたのは、明治生まれの石油技術者・山内肇でした。山内は、戦前・戦中を通じて東南アジアの油田開発に従事してきた経験豊富な技術者でしたが、戦後は、第一線から退き、葉山の海で趣味の釣りを楽しんでいました。
小説『ヤマ師』より引用(P314〜316)
太郎は1958年9月、山内を高輪の料亭に呼び出した。
「山内くん、戦時中は東南アジアで油田開発をされていたそうだね。南方の油田は日本の生命線であると同時に、最前線の戦場だっただろう」
太郎の問いかけに、山内はしっかりと頷いた。
「ベトナム、ボルネオ、ビルマ、シンガポール……どこの油田も米英による総攻撃の的になりました。それでも燃料確保は軍部の最重要事項なので、決して撤退は許されませんでした」
「最後はどちらに?」
「昭和20年の3月、シンガポールです。そのとき帰還命令が下りましてね。フィリピンまで敵が迫り、もはやタンカーでの輸送は不可能だという判断から、内地の石油増産任務に就けとの命令でした。現地に仲間を残して帰るのは本当に辛かったですが、『任務のためだ』と自分に言い聞かせて日本に戻りました」
「そうか。無事で戻ってこられてなによりだ」
太郎の言葉を聞き、山内は料理に伸ばしかけた箸を止めた。その箸をゆっくり箸置きに置くと、遠い記憶をたどるように視線を虚空へ向けた。
太郎は1958年9月、山内を高輪の料亭に呼び出した。
「山内くん、戦時中は東南アジアで油田開発をされていたそうだね。南方の油田は日本の生命線であると同時に、最前線の戦場だっただろう」
太郎の問いかけに、山内はしっかりと頷いた。
「ベトナム、ボルネオ、ビルマ、シンガポール……どこの油田も米英による総攻撃の的になりました。それでも燃料確保は軍部の最重要事項なので、決して撤退は許されませんでした」
「最後はどちらに?」
「昭和20年の3月、シンガポールです。そのとき帰還命令が下りましてね。フィリピンまで敵が迫り、もはやタンカーでの輸送は不可能だという判断から、内地の石油増産任務に就けとの命令でした。現地に仲間を残して帰るのは本当に辛かったですが、『任務のためだ』と自分に言い聞かせて日本に戻りました」
「そうか。無事で戻ってこられてなによりだ」
太郎の言葉を聞き、山内は料理に伸ばしかけた箸を止めた。その箸をゆっくり箸置きに置くと、遠い記憶をたどるように視線を虚空へ向けた。