そんな中、都市計画でブームになっていたのが高架上をゴムタイヤで走行する新交通システムだ。道路と一体的に整備することで建設省の補助を得られる上、導入空間を確保しやすく、地下鉄より建設費が安い。広島市は1977年から本格的に調査を開始し、1986年に建設省の新規路線として事業採択。1994年に広島高速交通「アストラムライン」として実現した。
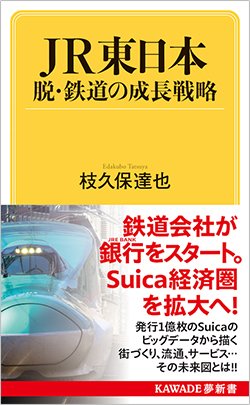 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
アストラムラインは道路空間の有効活用と都市景観の観点から、新交通システムとしては初めて地下区間(新白鳥~本通間)を設けた。この区間の建設費には運輸省の「地下鉄補助」が交付されており、広島初の地下鉄と言われることがある。それだけで「地下鉄」と言えるかはさておき、本稿で見てきた歴史的経緯を踏まえると、広島地下鉄計画の系譜にある交通機関であることは間違いない。
1990年代に入ってからも、東西線西広島~広島間(地下鉄、新交通システムまたは路面電車の地下化)、アストラムラインの本町以南延伸、西部丘陵都市線(広域公園前~西広島間)が提案された。
西部丘陵都市線は長い検討、調査を経て2024年に整備が決定し、2036年頃の開業を目指しているが、その他の路線はバブル崩壊後の旅客需要減少で実現しなかった。これ以降、中心部の路面電車を地下鉄(新交通システム)置き換える話は出ていない。
広島市民が最終的に選んだのは、JR、アストラムライン、宮島線が郊外輸送・中長距離輸送を担い、路面電車とバスが短距離のきめ細やかなサービスを提供とするネットワークだったのである。玄関口たる広島駅ターミナルビルへの乗り入れは、それを象徴する事業だったと言えるだろう。







