彼の命に従って働くために、自分の意志を捨て、自分をいじめ、自分を殺さねばならない。彼の快楽を自分の快楽とし、彼の好みのために自分の好みを犠牲にし、自分の性質をむりやり変え、自分の本性を捨て去らねばならない。彼のことば、声、合図、視線にたえず注意を払い、望みを忖度し、考えを知るために、自分の目、足、手をいつでも動かせるように整えておかねばならない。
はたしてこれが、幸せに生きることだろうか。これを生きていると呼べるだろうか。
-エティエンヌ・ド・ラ・ボエシ『自発的隷従論』山上浩嗣訳(ちくま学芸文庫)
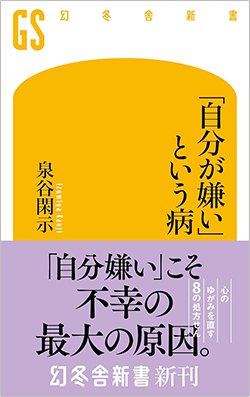 『「自分が嫌い」という病』(泉谷閑示、幻冬舎新書)
『「自分が嫌い」という病』(泉谷閑示、幻冬舎新書)
これは、16世紀フランスの若き学生ラ・ボエシが16~18歳の頃に記したもので、親友のモンテーニュに託されていたものです。当時の社会情勢に問題意識を向けた内容になっていますが、ここで問題にされていることは、親子の関係においてもそのまま当てはまる内容ではないかと思います。「仲良し親子」をやっている子どもは、この隷従をしている状態にあるのですが、それに当人は無自覚である場合がほとんどです。つまり、「いや」を禁じられ精神的に去勢されただけでなく、もう親の価値観や好みにすっかり迎合し、親なしでは生きていけないといった依存状態に陥ってしまっているのです。
「はたしてこれが、幸せに生きることだろうか。これを生きていると呼べるだろうか」というラ・ボエシの言葉が、痛烈にそういった隷属状態の人間に向けられているのです。







