そこには、SBIホールディングス(HD)による新生銀行に対する敵対的TOBが影響しています。
SBIHDは2021年9月10日、新生銀行に対するTOBを開始しました。このTOBは新生銀行の取締役会の賛同を得て行われたものではなく、いわゆる敵対的TOBでしたが、結果、成功しました。
銀行再編を仕掛けるように見せつつ
しっかり高値で売り抜いていた
一方、このTOBの過程においては、旧村上ファンドが新生銀行の大量保有報告書を提出したという出来事がありました。そのため、旧村上ファンドが先述の地銀5行の大株主として登場したことを受けて、旧村上ファンドが地銀再編を目的に株式を取得したのではないかと考えた投資家がいてもおかしくありません。
株価の急騰は、そのように見た投資家が実際にいた可能性を示唆しています。
しかし、冷静に地銀各行の株主構成を見てみると、決して地銀再編が容易なものではないことがわかります。各行ともに安定株主比率が非常に高く、旧村上ファンドがいくら株式を取得しても、業界再編を強要されるような株主構成ではないし、敵対的買収を仕掛けても容易に成功するようなものではありません。
なおかつ、銀行の株式を20%以上取得する場合、金融庁長官の認可が必要ですSBIHDが新生銀行にTOBを仕掛けた時は認可を取得しましたが、旧村上ファンドが20%以上の株式を取得しようとした際、金融庁長官は認可するかどうかはわかりません。
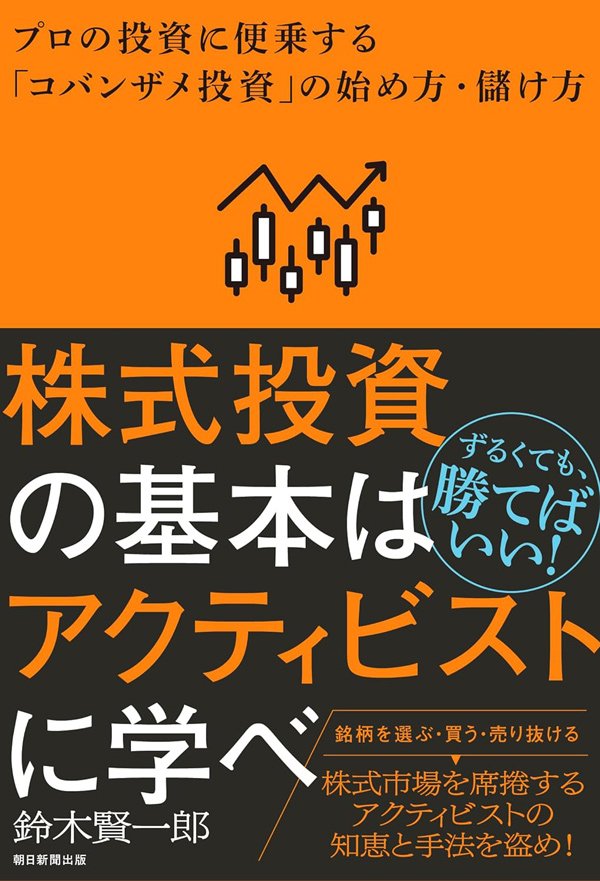 『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』(鈴木 賢一郎、朝日新聞出版)
『株式投資の基本はアクティビストに学べ プロの投資に便乗する「コバンザメ投資」の始め方・儲け方』(鈴木 賢一郎、朝日新聞出版)
つまり、株主構成や銀行を取り巻く法規制を勘案すると、地銀はアクティビスト主導での再編が難しい業界であるということがわかるのです。
実際、2023年3月末には、旧村上ファンドは先述の地銀5行の大株主ではなくなっています。旧村上ファンドに地銀再編を手掛ける意図はなく、株価が急騰したところで売り抜けたと思われます。
アクティビストは、株式市場や投資家から自分たちがどう見えているのか、自分たちに投資家が何を期待しているのかも熟知していて、それさえも自らの投資機会の創出に活用しているのでしょう。







