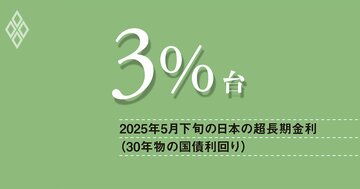バブル崩壊後、日本経済は物価上昇率がほぼゼロかマイナスになった。
企業の設備投資は縮小し、個人消費も伸び悩み、賃金は上がらない。結果として税収は増えず、景気対策としての財政出動を繰り返した結果、債務が雪だるま式に膨れ上がった。
1990年代後半には、日本経済は新たなデフレ要因がデフレ状態をさらに悪化させる、いわゆる「デフレ・スパイラル」に陥り、日本発の世界恐慌が懸念されるほどの深刻な金融危機に見舞われた。
当時は小渕政権(1998~1999年)の大型財政出動によってなんとか乗り切ったが、2000年代に起こったITバブルが弾けると、日本は再びデフレに突入した。
この悪循環からの脱却を目指したのが、2010年代に安倍晋三元首相が打ち出した「アベノミクス」である。
黒田日銀と協調しての前例のない大胆な金融緩和、機動的な財政出動、成長戦略という“三本の矢”を実行し、賃金が伸び始めた。
だが、マイナス金利という「禁じ手」まで使っても実質賃金はさほど伸びず、2%のインフレ目標も達成できないままに、アベノミクスは中途半端に終わった。
それはアベノミクスの本質である「円安政策」に企業が堪えきれなくなったことや、二度にわたる消費税増税の影響があった。“三本の矢”のうちの「財政出動」が、社会福祉費などの増大で機能しなかったことも大きかった。
デフレ脱却のきっかけは
コロナ禍と資源インフレ
その膠着状態を破ったのは、意外にも新型コロナウイルスによるパンデミックであった。
2020年以降、世界中で経済活動が制限され、各国が異例の財政出動と給付を行った結果、急激なインフレが進行した。
日本も例外ではなく、2022年以降は消費者物価指数(CPI)が上昇を続け、長らく未達だった2%のインフレ目標をようやく超えた。世界的なインフレ波に巻き込まれるかたちで、日本は長年のデフレから解放されたのである。