「旧東ドイツだったビッターフェルトにおいて、初めての自由投票で誕生した市長」であること、「壁が崩壊した後の市政をまとめた功績」によって、市がお墓を残すことになりました。
祖父は祖母の死の2年後に再婚し、相手の女性と共に入るお墓を別に買っています。
つまり、もし、タニアさんの祖母が公人でなかった場合、契約を延長せずに「おしまい」にする可能性もあったわけです。
お墓に人生を縛られるのは
現実的じゃない
「お墓は亡くなった人が永遠に眠る場所」という感覚が強い人にとって、「賃貸契約を延長する・しない」のシステムは「ドライ」に感じられるかもしれません。でも私は「20年」という期間は現実的だと思いました。
お墓といえども、故人のことを知っている人、故人のことを定期的に思い出す人がこの世にいなければ、形が残っても忘れられてしまいます。なぜならお墓は「残された人たち」が故人を偲ぶ場所でもあるからです。
賃貸制のお墓の場合、亡くなった20年後に契約を延長しないと決めても、全部がなくなってしまうわけではありません。現実的なことを書くと、確かにかつてお墓があった場所には「ほかの人が入る」ことになりますが、故人の氏名と生年月日、その人へのメッセージを書いたものを、他の家族や親戚の墓石があるところに残すことができます。
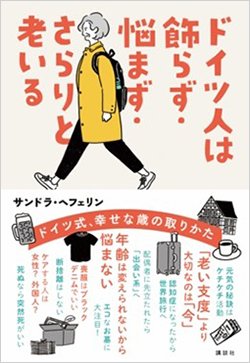 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』(サンドラ・ヘフェリン、講談社)
『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』(サンドラ・ヘフェリン、講談社)
まだ30代のタニアさんは、自分のお墓について深く考えておらず、こう語ります。
「私がもしも若くして旅立った場合、自分の死後、配偶者にどんな出会いがあるかわからないでしょう?かなり歳を取って亡くなったとしても、その時子どもがどうなっているかは、もっとわからないと思う。だから、予め自分のお墓などについて『がんじがらめ』になって決めるのはあまり現実的なことではないのかもしれない」
こうして考えてみると、ドイツの「期間限定・賃貸の墓のシステム」も1つのヒントのような気がします。
「永遠」というものは、墓という形ではなくても、人の心の中にあれば良いと、私は感じました。







