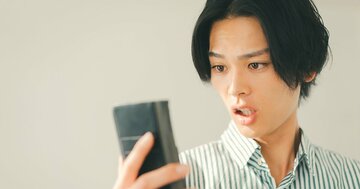その際、怒りを観察する視線は、科学者が研究対象を眺めるような、やや距離のある視線を心がけます。怒りを観察し、その強度をモニターして0から10の数字で評定します。
「今の怒りは7だな」とか「8かも」といった具合です。これは量的な観察ですが、より細やかに質的な観察をすることもできます。怒りの質感を丁寧に感受し、繊細に言葉にするのです。
「イライラ」「はらわたが煮えくり返る」「激おこ」など、実際に言葉にしていって、それがフェルトセンス(体に感じられた感覚)とピッタリくるかどうかを自分に問いかけます。そして、しっくりくるまで続けるのです。
深い呼吸や脱力だけで
副交感神経は働きだす
最後に、リラクセーションをする方法です。
怒りに駆られているときには、自律神経系の交感神経が優位になっています。自律神経系は、交感神経と副交感神経の2つのバランスで成り立っています。意図的に副交感神経を活性化すれば、交感神経が鎮静化され、怒りが鎮まることを期待できます。
自覚的に深く息を吐くこと、意図的に肩の力を抜くこと、地面を踏みしめ、地面の感触をじっくり感じること(グラウンディング)、「大丈夫、大丈夫」などと落ち着く言葉を心の中で繰り返し唱えること、ペットの猫や雄大な自然などの落ち着くイメージを心に呼び起こすことなどが挙げられます。
激しい怒りに駆られるような状態は、反射的に「闘うか逃げるか」反応を引き起こす状況です。それ自体を抑えるのは非常に難しいでしょう。
そのため、とりあえずは闘うことを避けて、その場を離れる(その場から逃げる)のが最も効果的です。その上で、怒りの対象から注意を引き離したり、怒りの感情を外側から観察したり、リラクセーションをしたり、もしくはこれらの対処法を組み合わせて、徐々に落ち着くようにしていきましょう