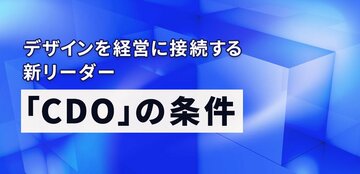100年続く会社の組織変革
反対勢力にはどのように対応したのか
 YO SUZUKI
YO SUZUKIグローバル刃物メーカーの貝印にてCCO/CMOとしてマーケティングとデザインを統括。スウェーデンのクリエイティブ企業、グレートワークスでもCCOを兼任。近年は、クリエイティブディレクターとして、国内外で表現制作や企業プロモーション制作を行いながら、俳優の夏木マリ氏のパフォーマンス「PLAY×PRAY」の動画演出や舞台背景の制作、漫画家のタナカカツキ氏が手掛ける「渋谷SAUNAS」のエグゼクティブアドバイザーもつとめるなど幅広く活動。2019年には、ForbesJapan誌「世界を変えるデザイナー39人」に、2021年には日経「マーケターオブザイヤー2021」にも選出。グルーミングブランドAUGERのブランドディレクター。
Photo by YUMIKO ASAKURA
勝沼 そのような組織変革の方向は、経営トップのビジョンとそろっていたのですか。
鈴木 現在の社長(遠藤浩彰氏)は、副社長だった時代から、企業経営にはブランドやデザインの視点が必要であると考えていました。僕がこの会社に呼ばれたのは、その考えを現実化するためだと思っています。
しかし、貝印は100年以上続いている企業なので、組織は一朝一夕に変えられるものではありません。そこで、まずは広報宣伝部に足場を置いて、そこから徐々に担当する組織を広げていくという道筋をつくってもらいました。
勝沼 それでも反対する人はいたんじゃないですか。
鈴木 もちろんです。まず、すっと理解してくれた部門の変革に全てを注ぎ込み、その間、急激な変化に慎重な人には、説得に時間をかけるのではなく、実績を示そうと思いました。グルーミングツールブランド「AUGER(オーガー)」や、包丁ブランド「関孫六」に「マスターライン」というシリーズを立ち上げるなど、新しいブランドが市場に浸透していくという結果を見せることで、リバーシの石をひっくり返すように社内の賛同者を増やしていきました。
気をつけたのは、「デザイン畑の人間が組織を牛耳っている」という印象を持たれないようにすることです。外から来たデザイナーが組織をハンドリングするということへの違和感は理解できます。組織変革の客観的な必要性を丁寧に説明し、実績を見せることで一つ一つ納得してもらいながら、徐々に変革を進めてきたという感じです。
勝沼 一方で、「デザイン畑の人間」だからこそ組織を動かすことができたという側面もありそうです。
鈴木 0から1を生み出す力は、間違いなく強みになりました。僕が来てからは、プロトタイピングの量とスピードを極端に上げ、時には社内で山ほどボツにしました(笑)。でも、そのボツの山こそが組織を動かす燃料です。例えば、刀のような処理形状の包丁。最初は「作りづらい」「高い包丁なんて売れない」と言われました。そこで、この形状がどれだけ引き切りに適しているかを示すため、人にセンサーをつけて筋肉の動きを測定し、切れ味を科学的に証明しました。その結果、ブランド戦術の一部として市場に出すことができたのです。
デザイナーが手を動かし、目に見えるプロトタイプを作って、それを示してフィードバックを得る。それを繰り返すことで、デザインの力を理解してもらうことができたと思っています。だから僕は、デザインを「無から作り出す武器」として位置付けています。
勝沼 デザインの役割自体が変わったということなのでしょうね。開発チームなどから依頼されて商品の形や色を考えるという「受注的役割」から、あるべきブランドやデザインの在り方をデザイナーが自分たちから考えていく「提案的役割」に。
鈴木 おっしゃる通りですね。僕はデザイナー自身が「未来を引き寄せる」ことが必要だと思っています。ブランドが成長していく未来像を考え、それをデザインによって具体像にしていくということです。そのためには、デザイナーにもマーケティングの発想が求められます。それが、マーケティングの組織内にデザイン部門があることの意味です。