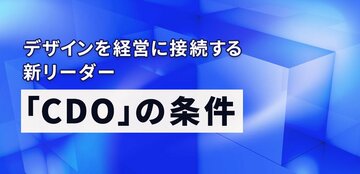リーダーが前向きであり続けるために
捨てなければならないものとは
勝沼 お話を伺っていると、デザインがまさに企業活動をけん引しているという印象があります。
鈴木 組織や風土を変える力が、デザインには間違いなくあると思います。しかし、その力を十分に発揮するためには、気を付けなければならないこともいろいろあると感じています。
まず大切なのは、デザイナーがデザインというフィルターの中に閉じこもらないことです。デザインを常に開かれた状態にして、誰もが理解できるものにしておく必要があります。そのために大切なのは、言葉の使い方です。デザインの専門家にしか理解できないようなデザイン用語を避けることはもちろん、できるだけシンプルな表現に努めるべきだと思います。
勝沼 デザイナーにとっての言葉の重要性は、僕も常々実感しています。言葉一つで、ぱっと理解される場合もあれば、逆の場合もありますよね。
鈴木 僕が意識しているのは、常にポジティブな言葉を使うことです。例えば「人が思い付くことはだいたいできる」という発想をベースに話すと、議論は自然と前向きになる。新しい挑戦に対しても、「できない理由」ではなく「どうすればできるか」に話が向かいます。そうすると、聞く側も「じゃあ、やってみようか」という気持ちになりやすいんです。
勝沼 いや、それすごく共感します。開発や企画の現場で、「できない理由」ばかり並べられると、そこで思考が止まってしまうんですが、逆に「どうすればできるか」を一緒に考え始めると、チーム全体が前向きに動きだすんですよね。社内の空気をそうやって変えていくのも、CDOの大切な役割だと思いますが、どうやったらそんなに前向きになれるんですか。
鈴木 何でしょうね……。会社における自分の立場や、役職、個人の成功に執着がないということはあるかもしれません。「会社をクビになったら困る」とか、「この立場を失いたくない」とか、「異動になったら嫌だな」といった気持ちに縛られると、判断や行動が小さくまとまってしまいます。
それから、自分の成功と他人の成功をリンクさせないことも大事です。僕はデザインをするときに、「次の工程で内部構造が作りやすいように」などと考えています。他部署が仕事をしやすい形に整えておけば、全体として成果が出やすくなりますから。
立場を失ってもいいと思えれば、「失敗してもOK」「自分の手柄にこだわらなくてもいい」というマインドになれる。そうなると、A案とB案を同時進行で走らせるとか、普通なら二の足を踏むような手も打てます。執着を手放すことで、組織にとっても自分にとっても、動きやすい環境が自然と整っていく気がしますね。