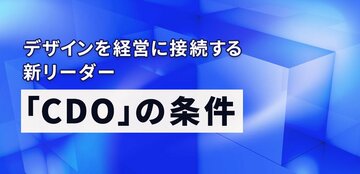勝’s Insight:自分の手柄を超えて、デザインを組織成果へと昇華するCDOの資質
<インタビューを振り返って>
鈴木さんの話の中で、私が特に興味深いと感じたのは、デザイン部門とIP部門が実に年100回ものコミュニケーションを重ねていることである。
デザイン部門はプロトタイピングを積極的に進め、世の中の一歩先を見据えた製品を形にしていく。その動きを受けてIP部門は、特許性の高い要素を拾い上げ、知財化の道筋へとつなげる──。言葉にすれば当たり前のように聞こえるかもしれないが、現実にはこうした緊密な連携が成立しているケースは極めてまれである。だからこそ、このチームプレーの確かさに強く引き付けられたのだ。
プロダクトやサービスの開発担当者にとって、特許になり得る要素は意外なものであることが多い。それを発見できるのはデザイナーではなく、IPのプロである。その要素を見つけて部分的にでも特許化しておけば、それが後に競争優位性のあるプロダクトに結実することが期待できる。貝印ではその「デザイン×IP」の仕組みを、両部門が実に年100回以上ものコミュニケーションを重ねることで運用している。
社内のさまざまな機能とコラボレーションすることで、デザインはさらに競争優位性を生み出すことができる。貝印の取り組みは、その実践例の一つとして大いに着目されるべきである。
もう一つ、私が注目したのは、鈴木さんの「自分の手柄にこだわらない」というひと言だ。
自分がデザインを担当した製品が売れた場合、「デザインがいいから売れた」と考えるのか、「売れた要素の一つがいいデザインだった」と考えるのか――この差は極めて大きい。
製品が売れるためには、事業部をはじめとしたさまざまな部署の力が必要だ。その総合的な成果が売り上げである。デザインもその一要素にすぎない。にもかかわらず、売り上げをデザインの力だけで説明しようとするデザイナーは、全体が見えていないといえる。
自分の手柄にこだわらない姿勢は、デザインが成功の一要素であるという視点につながる。そう捉えられるからこそ、成功に対してデザインがどのように寄与したかを明確に言語化できる。そして、その言語化ができれば、方法論として横展開でき、次なる成功を引き寄せることができる。
鈴木さんのひと言と、そこから導かれる構造を重ねたとき、CDOとして重要な資質が見えてきたように思う。
(第13回に続く)
 Photo by YUMIKO ASAKURA
Photo by YUMIKO ASAKURA