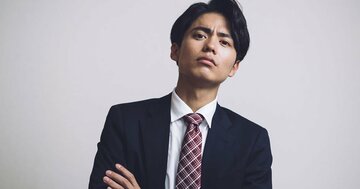――一度きりしか行ったことのない場所だと、その記憶はわりと信頼できますけど、何度も訪れてる場所だと、あのときどこをまわったか、あの人と行ったのはどこだったかとか、そういうことがどうしても混乱してしまうんですね。
「なるほど、そうかもしれません」
――奥さんとの間では、似たようなやり取りがしょっちゅうあるでしょうから、最も記憶が混乱しやすいと言えます。しかも、お互いに関心が違う方を向いてると、記憶に残ることもズレてたりしがちになります。
「たしかに妻との間では、子どもを連れてどこに行こうとか、今度の日曜はダメだとか、その次の日曜なら大丈夫だとか、似たようなやり取りがよくありますね」
――だからこそお互いに記憶が混乱しやすく、記憶のスレ違いが起こりやすい、っていうことがあるわけです。
記憶する人の心のありようで、つくられる記憶は違う
そこで、記憶の揺らぎやすさということについて、つぎのような解説をした。まずはじめに指摘すべきは、記憶は過去の単なる記録ではないということである。つまり、記憶というのは能動的につくられるもので、同じ出来事を経験しても、記憶する人の心のありようによって、つくられる記憶は違ってくる、ということである。
このことをもう少し具体的に説明しよう。多くの人は、記憶を過去の忠実な記録と思い込みがちである。だからこそ、他人の記憶と自分の記憶の間にズレがあると、相手の記憶が間違っていると思ってしまい、イラつくことになる。
かつては心理学の世界でも記憶をそのようにとらえていた頃もあった。「記憶の貯蔵庫モデル」とも言われるが、出来事を瞬間的に冷凍し、そのまま保存し、思い出すときに解凍する、ゆえにオリジナルな出来事がそのままの形で引き出される、というように考えられていた。
しかし今では、記憶はそのような受け身の心理プロセスとは考えられていない。記憶というのは、オリジナルな出来事とは別物であり、記憶する人によって能動的につくられるとみなされている。