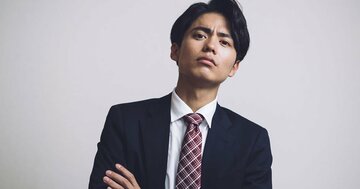「選択的知覚」という心理メカニズム
そもそも記憶するのは知覚された出来事なのだが、その知覚さえもが能動的につくられている。つまり、見る人によって違う見え方になっている、聞く人によって違う聞こえ方になっている。
たとえば、ショーウィンドウの中を覗き込んで、そこに飾ってあるマネキンが身につけている服を眺めているとする。そのとき、ショーウィンドウに映っているはずの自分の姿は見えていない。だが、自分の身なりを整えようとしてショーウィンドウに映る自分の姿を見ているときは、ショーウィンドウの中のマネキンもその服装も見えていない。
カメラで写せば、マネキンと自分の姿が二重写しで撮影されているはずであり、網膜にも二重写しで映っているはずである。でも、私たちは、とくに関心のある刺激、自分にとって意味があると思われる刺激に絞って知覚する。
つまり、知覚には能動的な取捨選択が伴うのだ。その取捨選択は無意識のうちに行われる。ゆえに、人によって知覚しているものにズレが生じる。
ある視点をとればマネキンの服装が見える、別の視点に立てば自分の服装が見える。どちらが正しくて、どちらが間違っているという問題ではない。どちらの方が自分にとって意味があると感じるかによって見え方が違ってくる。これが「選択的知覚」という心理メカニズムである。
このようにして知覚されたものを記憶するのだから、記憶にもズレが生じるわけである。
同じ経験をしても人によって記憶が違う理由
 榎本博明『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』(日経プレミアシリーズ)
榎本博明『なぜあの人は同じミスを何度もするのか』(日経プレミアシリーズ)
こうしてみると、同じ出来事を経験しても、人によって記憶していることが違うのは、当然のことなのだ。興味を感じているところが違えば、覚えていることも違う。同じ話を聞いても、関心をもって聞いているところが違えば、覚えている内容も違う。人によって知覚する視点が違うのだから、記憶していることが違うのも当然のことなのである。
そう考えれば、身近な人たちとの間で記憶のスレ違いがしばしば起こるのも、仕方のないことなのだとわかるだろう。興味・関心の違い、利害の違い、立場の違いといったものが視点の違いをもたらし、記憶にスレ違いを生むのである。
早く納入してくれないと困ると思っている人の心の中では、交渉中に出てきたいくつかの納期のうちの早い方の時期が記憶に刻まれやすい。納期までできるだけ時間的余裕がほしいと思っている人の心の中では、交渉中に出てきたいくつかの納期のうちの遅い方の時期が記憶に刻まれやすい。そのため双方の記憶にスレ違いが生じることになる。
一緒に旅行した友だちとの間の記憶のスレ違いにも、同じような心理メカニズムがかかわっている。先の例でいえば、寺院に興味のある人の場合、その寺を訪れたという記憶が鮮明に残っていても、寺院より景色や食事に関心のある人の場合は、そんな寺に行った記憶はない、といったスレ違いも起こってくるのである。