榎本博明
「感じのいい人」だと思っていた相手に、ある日突然、足をすくわれる――。親切にしてくれていたのに左遷後は冷淡になった、陰でひどくこき下ろされていた、自分の発言をねじ曲げて噂を流された。そんな「裏表人間」は、あなたのすぐそばにもいるかもしれない。危険人物を見分けるためのサインとは?

「自分には価値がない」「どうせうまくいかない」……自己肯定感の低さから、自分に自信が持てず、生きづらさに悩む若者が多くいます。しかし、日本の若者の自己肯定感は本当に低くて問題なのでしょうか。筆者が注目するのは、複数ある国際比較調査。データそのものではなくその「読み方、解釈」です。国際比較調査データを正しく読み解けていないことにより、見当違いな教育政策やメディアが「生きづらさ」をもたらしている面もあるのでは?と指摘します。
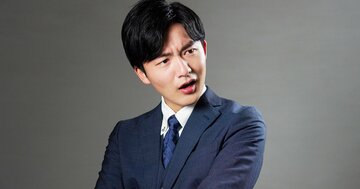
どこの職場にも“とにかく愚痴が多い人”というのがいるものです。あまりにも愚痴ばかり言っているので「あの人に捕まると、しばらく愚痴の聞き役にされてしまう」「愚痴ばかり聞かされるのでストレスが溜まり、こっちのモチベーションまで下がってしまう」などと、周囲から煙たがられるほど。仕事が大変だったり、イヤな思いをしたり、というのは誰でも多かれ少なかれあるはずですが、こういう人は、本当に嫌な目にばかり遭っているのでしょうか?なぜ愚痴が増えるのか、その理由に迫ります。
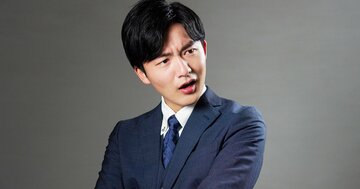
親は頭がいいのに「子どもは勉強ができない」そんな親子が珍しくない当然の理由〈再配信〉
「勉強ができるようになりたい」~学生の頃、一度はそう思ったことがあるのではないだろうか。どうやったら勉強ができるようになるのか。親ゆずりの知能が高ければいいのか?しかし、知能が高くても「学ぶ力」がなければ勉強ができるようにはならないのだ。学ぶ力とは何か、三つの側面から考えてみたい。

モチベーションは高く、仕事もできるのに、“うっかりミス”が多い人がいる。性格だから仕方ないとは思うものの、仕事に支障が出ることもあるので、何とかならないものか。そんな悩みを聞かされることがある。なぜうっかりミスをするのか、どうしたら直るのか?それについて考えてみたい。

「お金の見え方」で即バレ!お金に執着する人の意外な特徴
とくに自分から希望したわけではない業務に「あなたがやりたがっていた件だから…」とオファーされる。あるいは、レストランで別の料理を注文したはずなのに、注文した覚えのないシェフのお勧め料理のオーダーが入ってしまっている。こうしたスレ違いは職場でも日常生活でもしょっちゅう起きるが、その背後には「記憶にはその人の欲求が絡みがちである」という心理メカニズムが働いている。

なぜ妻は「身に覚えのないこと」で責め立てるのか?家庭内トラブルの意外な真相とは
取引先や配偶者など、身近な相手との間における、どうにも理解不能な記憶のスレ違いは、だれもが経験したことがあるのではないか。絶対にそんなことは言ってないのに、「言った」と言って譲らない。あるいはまったく聞いていないことを「たしかに伝えた」と相手に自信たっぷりに主張される。このような「言った・言わない問題」はどのようなメカニズムで起こっているのか?

自分がミスをして迷惑をかけたら、「すみません」「申し訳ありません」などと謝るものだが、最近は決して謝らない人がいて困る、という管理職や経営者の嘆きを聞くことが多い。ミスを繰り返し、指導のために注意すると逆ギレする人までいる。こうした「絶対謝らない人」は、なぜ謝らないのだろうか?実はこういう人たちは、注意する側が思いもよらないような考え方、受け止め方をしている可能性がある。彼らが「謝らない理由」を4つ、説明しよう。

「そんなことは聞いてない!」言ってることが180度変わる上司は何を考えているのか?
自分で指示をしておきながら、何か問題が起きたら「そんな指示をした覚えはない」とうそぶく。あるいは、ちゃんと報告をしているにもかかわらず、「そんなことは聞いていない」と涼しい顔をする。なぜ職場ではこのようなケースが絶えないのか。厄介なのは、意図的に責任逃れをしようというずるさをもたない人物であっても、悪気なく記憶が変容してしまうことがあるという事実である。

若い頃に60歳というと、もう人生の終着駅を間近にしたご隠居さんといったイメージを持っていたのではないか。でも、自分がいざ60歳になってみると、あるいは60歳を目前にしてみると、自分がそんな年齢になっているといった実感がなく、戸惑いを覚えるものである。これからどう生きていくのがいいのか考え込んでしまう……それが多くの人の現実だ。人生の大きな転機をどう乗り切ればよいのだろうか。

職場で「すみません」を言えない人が増えている。ミスを指摘されると「先輩だってミスしたことあるじゃないですか!」と逆ギレする若手社員。謝罪どころか攻撃的な反応を示す部下に、管理職は困惑している。なぜ当たり前の謝罪ができないのか。その背景には、自信のなさ、比較意識、認知能力の問題など、複雑な心理的要因が隠されていた。
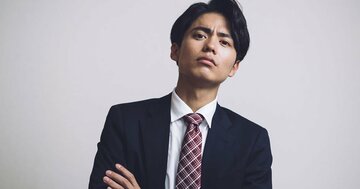
世間では「謝罪」が大流行りだ。不祥事や事故を起こした企業の謝罪、問題発言をした政治家の謝罪、不倫をした芸能人の謝罪……と、さまざまな謝罪の言葉や映像が世間にはあふれかえっている。しかし、こうした謝罪の言葉を聞いていると「本当に自らに非があると思っているのだろうか?」といぶかしく思ったり、うさん臭さを感じてしまうことも多い。「とにかく謝ればいいんだろう?」といった本音が透けて見え、「そんなもので納得できるわけがないだろう」とあきれてしまうのだ。「誠実な謝罪」と「いかがわしい謝罪」とはどこが違い、どうしたら見分けられるか。そして自分が謝る立場になった場合、謝意がきちんと伝わるよう誠実に謝るには何に気をつけたらいいのだろうか?

「自分は自己肯定感が低いからダメなんだ」という日本人の悩みが、あまりにも的外れな理由
自己肯定感は高くないとダメなのだろうか――。欧米諸国と比べて、日本の若者の自己肯定感が低いというデータがあるが、そもそも、自己肯定感がどのようなものなのか、どのように測定されるのかを知らないことは少なくない。本稿では、自己肯定感を測定する10の項目を紹介する。

「自分に満足」と答えた日本の若者はたったの4割!?米国と比べた「自己肯定感格差」の根本原因
日本の若者は自己肯定感が低いといわれている。内閣府が行った「我が国と諸外国の若者の意識に関する調査」(2018年)によると、「自分に満足している」と答えた若者は、欧米諸国が8割だったのに対し、日本の若者は4割強しかいない。どの国際比較データをみても、欧米諸国と比べて日本の若者は飛び抜けて自己肯定感得点が低いのは事実である。それは、なぜだろうか?

仕事そのものの能力については問題ないのだが、コミュニケーションが苦手すぎるがために、せっかくの知識や能力を生かせていない人物というのがいるものである。こうした人材を戦力にしていくにはどのような対処が望ましいのだろうか。

「なぜそうやって仕事をするの?」頭がいいのに仕事ができない部下が答えた“とんでもない回答”
仕事をさせてみると頭が良いと感心するのに、なぜか判断を誤ることが多い人物がいるものだ。時には、そのミスが組織として致命的な問題につながりかねないこともある。能力が高ければ正しく判断できそうなものなのに、なぜ仕事上で大きな問題になるような判断ミスをしてしまうのか?実は、“判断”には、頭の良さや能力以外の認知要因が影響する。有能な人材をうまく生かし、組織のリスクを回避するコツを解説する。

やる気のない部下を抱えると苦労するが、やる気はあってもなかなか仕事ができるようにならない人物も困るものだ。いくらやる気があるとはいえ、温情で放置しておけば部署の生産性も士気も上がらない。何とか戦力になるように育てるには、どうしたらいいのだろうか?

「自分の人生は失敗だった」でも大丈夫、60代での“振り返り”が人生の価値を180度変えるワケ
前回、前々回と、人生の振り返りについてお話ししました。振り返りの中で「自分の人生は失敗だった」と思う人もいたかもしれません。同じような辛く悲しい出来事を経験しても、前向きに受け止める人もいれば、後ろ向きに受け止める人もいます。過去は変えられませんが、今後の人生の満足度や日頃の気分は、出来事の受け止め方次第で変わってきます。

60代を襲う不安に押しつぶされない!「悩みを話してスッキリする」 自己開示の心理的効用4つ
人はなぜ、悩むとだれかに話したくなるのでしょうか? それには、自己開示の持つ心理的効用が関係しています。本稿では、悩みを他人に語ることで得られる4つの心理的効用について説明します。

60代を超えて「人生の喪失期」に入る人と「第2の青春期」に入る人の決定的な思考の違い
人生100年時代、男女の平均寿命は80歳を超えました。仮に80歳まで生きるとして、60歳から80歳まで20年。余生とみなすにはあまりにも長いです。これからの人生を豊かにするために、まずは今までの人生を振り返ってみましょう。
