岩手県の県立高校ではそもそも「東大受験をしよう」とする人が少ない。東大に合格する人が少ないというよりも、東大受験をしようとする人の母数が少ない。東大を受験するという発想そのものが稀有な環境で育った三田先生にとって、東大は手の届かない存在だ。
一方で、佐渡島氏は灘高校から東大に合格した、いわゆる「エリート」と呼ばれるカテゴリーに属する人間である。灘高校は学年の半分以上が東大を目指す超エリート高校であり、そこの人間としては「東大は簡単」という感覚になるのも頷ける。都内に暮らしていれば、珍しいとはいえ、東大生の存在は認知できる。
少なくとも東京在住で「東大生・東大卒の人なんて会ったことがない」という状態は、あまりないと言える。関西近辺でも、大阪や京都に住んでいる人で「京大生・京大卒の人なんて会ったことがない」という人は少ないだろう。会ったことがあれば、必然的に目指すという選択肢も増えるだろうが、しかしそれが少なかったわけである。
受験に関する知識も、大きな差があった。地方に塾が作られていった背景があるとはいえ、SNSもまだそこまで発達しておらず、受験のテクニックなどはまだ全然知られていなかった。東大に行く選択肢もなければ、テクニックも知られていない、地域間格差がかなり大きい時期だったと言える。
「できない子」こそ東大を目指せ
地方の受験生に与えた多大な影響
まとめると、2000年代は特にこの地域間の教育格差・ギャップが大きく、三田先生と佐渡島氏の間にも大きな認識の違いがあった。だからこそ三田先生は「この企画はいける」と思ったというわけだ。あまり認識されていないことだが、『ドラゴン桜』は都心部ではもちろん盛り上がっていたが、それよりも地方でこそ人気だった。
都内の受験生の話であるにも拘らず、実際に影響を与えたのは都外の学校だったわけである。先程東大志望の人がかなり増えたという話をしたが、それも特に地方から東大を目指す人が増えたという背景がある。
実際東大生に聞いても、都内の学校から東大に来た人はこの作品をあまり見ていないケースも多いが、地方から東大に来た人はかなりの割合で認知している。
さて、「ドラゴン桜」は、今までの受験に対するイメージを壊すものだった。これは三田紀房先生が漫画で「常識と逆のことを言う」という技法を好んでいたことが要因の1つであり、漫画からドラマが作られるにあたってこの要素が強化されたと考えられる。
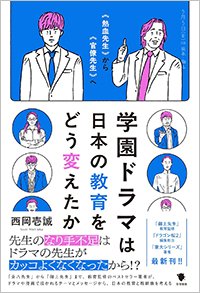 『学園ドラマは日本の教育をどう変えたか “熱血先生”から“官僚先生”へ』(西岡壱誠、笠間書院)
『学園ドラマは日本の教育をどう変えたか “熱血先生”から“官僚先生”へ』(西岡壱誠、笠間書院)







