 伝統の水田実習で使われる「ケルネル田圃」。奥には京王井の頭線が走る
伝統の水田実習で使われる「ケルネル田圃」。奥には京王井の頭線が走る
実倍率3倍台は維持しているものの、少子化は「筑駒」も直撃している。学区拡大の影響はどのように出たのか。農学校の系譜を引くため、水田を保有し、生徒が主体となってコメ作りする姿が受け継がれてきた。3日間にわたって高3が主導する文化祭ほか三大行事など学校文化も見ていこう。(ダイヤモンド社教育情報、撮影/平野晋子)
山田忠弘(やまだ・ただひろ)
筑波大学附属駒場中学校・高等学校中学副校長

1971年東京・新宿生まれ。筑波大学附属駒場中学校・高等学校(第38期)、東京大学文科III類から文学部英文科卒業。塾勤務の後、目黒学院中学校・高等学校と暁星中学校・高等学校に勤務、2008年に英語科教諭として入職。研究部長、中学学年主任、教務部長を経て、25年から現職。
通学区域拡大の影響
――筑波大学附属駒場中学校(筑駒)の受検者数が、ここ数年増加傾向にあります(2022年479人、23年521人、24年555人、25年532人)。通学区域の拡大が影響しているのでしょうか。
山田 片道1時間で通学できるという区域が基本で、対象となる路線が拡大するたびに検討しています。24年に中学校の通学区域(行政単位ごと)を見直しました。東京都内は変わりませんが、埼玉県はさいたま市の一部(浦和区、大宮区、北区、桜区、中央区、西区、南区)、所沢市やふじみ野市、草加市など、千葉県は習志野市、船橋市、松戸市が加わり、神奈川県ではこれまで区域外だった横浜市の泉区、港南区、戸塚区、南区の他、厚木市や海老名市、座間市も対象となりました。
――『令和7年度学校要覧』を見ますと、新しい通学区域から入学してきた生徒数(24年・25年)は、船橋市(1・1)と松戸市(1・0)、さいたま市(2・6)は大きく増加、横浜市(13・14)は微増ですね。
山田 昔は東京23区でも東側は対象外でした。通学区域拡大の影響は、しばらく様子を見ないと何とも言えません。
――既存の学区では、世田谷区(17・13)と港区(4・10)が2桁台で、他に杉並区(9・8)、大田区(3・7)、新宿区(0・6)、文京区(4・6)、目黒区(5・6)が比較的多く、後は分散している様子がうかがえます。
山田 以前、調査書を扱う部署を担当していたとき、文京区の特定の小学校からたくさん受けていたことが印象に残っています。受験生の多くはサピックスに通っているので、居住地は関係ないといえば関係ないのでしょうが。
――第1次選考で抽選になるのは、何人以上集まった場合ですか。
山田 募集人員の8倍程度です。最近は抽選による選考を行っていません。少子化の流れが止まらない以上、今後も抽選になることはないと思われます。
――中学校は募集人員120人の8倍で960人ですか。25年は出願者数が644人で、全員が第1次選考合格者数となり、2月3日に第2次選考を受験したのが532人で、131人が合格していますね。みな第一志望だと思いますが、慶應義塾や早稲田高等学院に入学し、辞退する例があると聞いています。
山田 開成が一番の競合校という感じはします。開成の新校舎の影響は多少あったかもしれませんが、何とも言えません。
――神奈川だと聖光学院も、でしょうか。共学校はいかがでしょう。
山田 慶應義塾はあると思いますが、あまり共学校と併願しているイメージはありません。私もこの学校の卒業生で、1984年中学入学の38期です。当時は2000人以上志望しており、抽選で半分はじかれていました。第一志望は麻布でしたが、抽選に受かったのでこちらも受けることができました。私のころは中学受験者の割合がそもそも少なかったですが、いまは優秀な子が中学受験をしないという選択肢がほぼないと思います。
――最近は難関校の受験生自体が減ってきています。
山田 受験塾である程度調整されているのか、あまり箸にも棒にもかからないという受験生はいませんね。40人を募集する高校の場合は、合格発表が遅めなこともあり、都立高校などにぎりぎりで抜けられてしまうこともあります。中学からの内部進学者の中に後から入ることを躊躇する人がいるかもしれません。高校は4クラスで、高入生は各クラスに10人ずつ入りますが、担任は入学後しばらくは注意して見守っています。
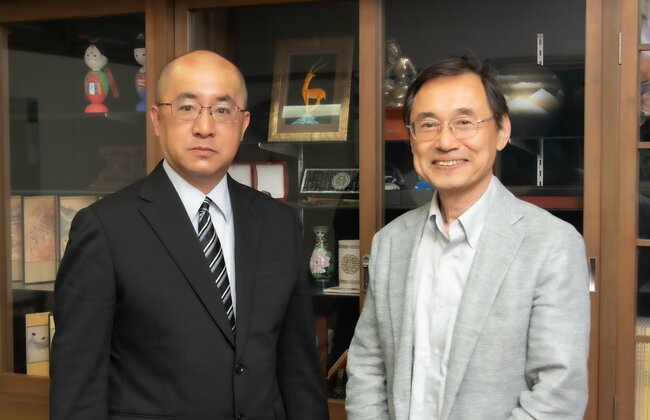 毎週の担任会で各学年の様子は分かるものの、部活も担任も外され、数コマの授業だけ残されるのはいささか寂しい
毎週の担任会で各学年の様子は分かるものの、部活も担任も外され、数コマの授業だけ残されるのはいささか寂しい







