農学校の系譜を引く「筑駒」の伝統
 緑の多い校内。桃や梅など、実のなる木も多い
緑の多い校内。桃や梅など、実のなる木も多い
――帰国生や国内のインターナショナルスクールに通う国際生への対応はいかがでしょう。私立では最後の方になりますが、開成も(学校教育法)1条校以外に門戸を開きました。
山田 中学では募集を分けていません。海外帰国生を分け募集している高校でも、入試問題は同じ。帰国生の割合を増やしたいということは特になく、特別な対応はありません。今後、公立学校などが35人学級になるかどうかが個人的には気になります。大学側は教員を増やす気はなさそうですから、募集定員をその分減らす可能性も考えられます。
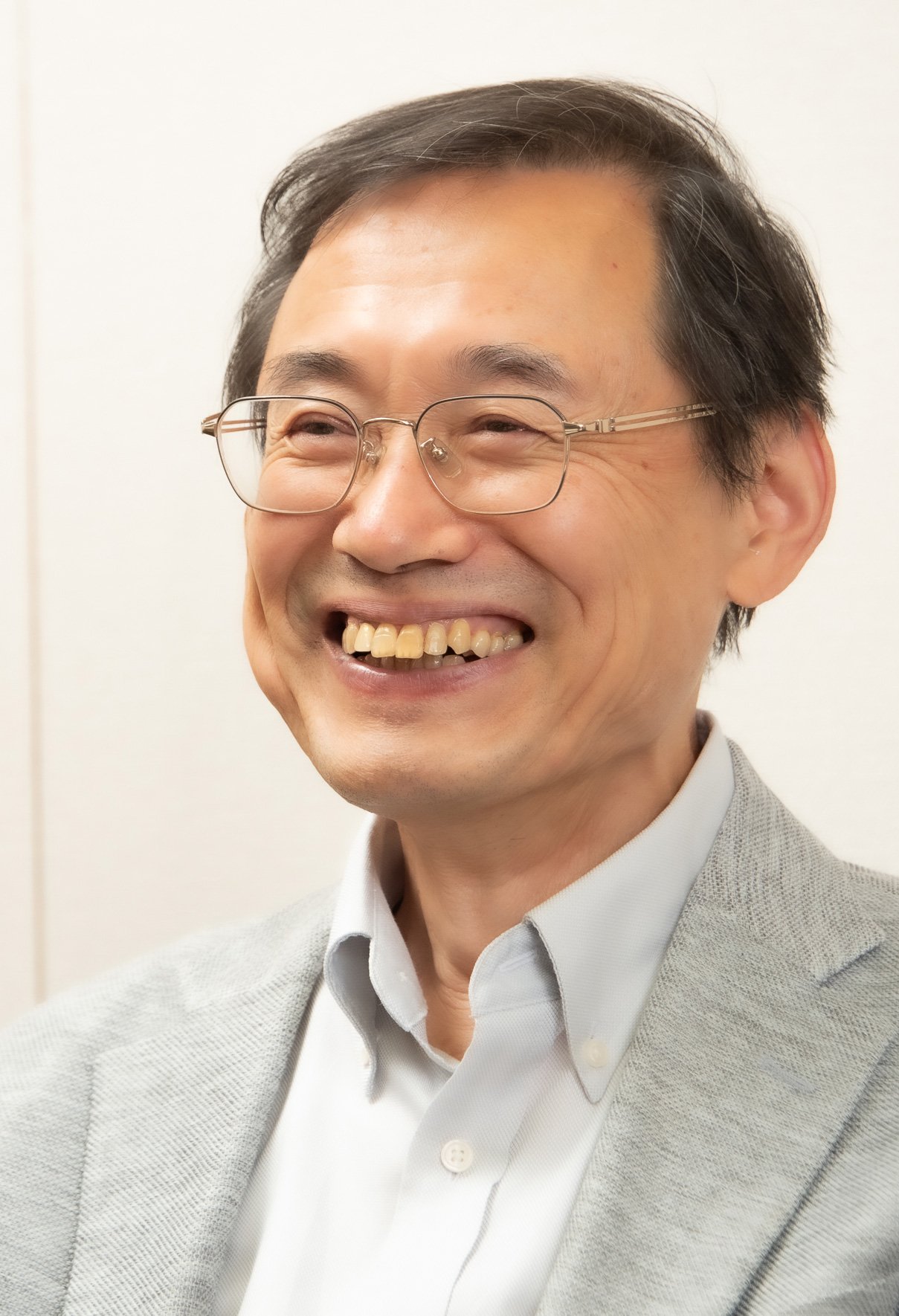 森上展安
森上展安(もりがみ・のぶやす)
森上教育研究所代表
1953年岡山生まれ。早稲田大学法学部卒。学習塾「ぶQ」の塾長を経て、88年森上教育研究所を設立。40年にわたり中学受験を見つめてきた第一人者。父母向けセミナー「わが子が伸びる親の『技』研究会」を主宰している。
――国立校なので授業料収入は関係ありませんし。私立では完全中高一貫化のため高校での募集をやめる学校も出てきています。こちらではそうした雰囲気は感じられませんけれども。ところで、入試問題は相変わらず大変に難しいですね。
山田 かつて、難問・奇問を指摘されたこともあり、その点は気をつけています。高校の英語問題では、語彙が学習指導要領の範囲を超えないよう心掛けています。スピーキングはありませんが、リスニングはあります。
――以前数学の先生に伺ったら、1人1問ずつ、1年かけて準備すると。数学はネタが尽きないのか心配してしまいます。
山田 教科会で持ち寄って、夏くらいから考えます。英語の場合は小説など題材を探したりします。
――報告書の100点と4科を合わせた500点満点で合否判定をしていますが、中学でも英語を入試に加えることはありそうですか。
山田 中学での英語入試はいまのところ考えていません。小学校によって卒業時のレベルがばらばらなので、中学ではゼロに近いところからというスタンスです。
東大の過去問は塾などで扱うことが多いので、授業は、高校なら小説の原書を少しずつ区切って読んだりします。ものによっては大学入試よりも難しいので分からなくて当たり前、分かるところをつないで全体としてストーリーをつかむよう指導します。国語力がないと難しいですね。
――ネイティブの先生もいるのですか。
山田 週に1回、英語科教員とネイティブ教員によるチーム・ティーチングがあります。とはいえ、40人クラスなので、話す機会がそれほどあるわけでもないです。
――構内で生徒さんを多く見かけましたが、みなさんスラッとしていますね。『学校要覧』を拝見すると、年齢別裸眼視力(視力の悪い方を基準)の中1生は74.5%が視力0.3未満で、全国平均23.3%の3倍以上。過酷な受験生活を送ったのだなと思いました。
山田 身長は全国平均より少し高く、あまり肥満の生徒はいないかもしれません。今朝は高1の生徒が草取りをしていました。6月の田植えと10月の稲刈りも中1と高1が担います。4月に種まきして温室で苗になるまで育て、耕起から脱穀・籾摺(もみす)りまで、「水田学習」は総合的な学習の時間に生徒自ら行っています。
――京王井の頭線の線路際にあるケルネル田圃を引き継いだ駒場水田ですね。どのくらいの広さですか。
山田 1500平方メートルあります。収穫したお米で12月に餅つきを行い、3月の卒業式と4月の入学式で配る赤飯にも利用しています。
――もち米でしたか。筑駒は駒場農学校の系譜で、近代農学発祥の地。校長は筑波大学の生命科学系の教授が代々担っていますね。
山田 校長は原則週2回の出勤です。校章は麦の穂をデザインしたもの。中3は技術・家庭科の授業で、校内にある畑にサツマイモを植えています。
 手前にサツマイモ畑、奥にはイネの苗まで育てる温室
手前にサツマイモ畑、奥にはイネの苗まで育てる温室







