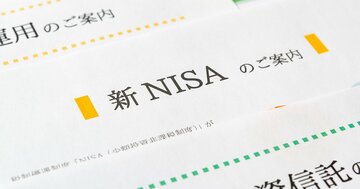その意味で、ご自身のリスク許容度は、「あらかじめ決めておく」ことが必要となるのですが、これは「言うは易く、行なうは難し」です。
なぜならば、それは常に、「自分の欲との戦い」でもあるからです。
たとえば、私が分配金生活を始めた2024年4月頃のマーケットは、どうだったかというと、基本的に右肩上がりの状況が続いていました。つまり、「投資すればするほど、より多くのリターン、つまり分配金が手に入る」という状況だったのです。
となると人間(私だけとは思えませんが)はつい、欲張りになるものです。そう、手元の現金はすべて、投資信託へと注ぎ込もう、ということとなるわけです。
元本2000万円のリターンは
手取りで月30万円
実際のところ、それは、ほぼ1年間はうまくいっていましたから、一概に間違っていたとは思えません。現実に、その間に、いわゆる種銭である2000万円でのリターンは、税引き後の手取りで月30万円ほどでしたから、年間にして360万円の「追加のじぶん年金」を手にしたことになります。
前著(『定年いたしません!』光文社新書)でもご紹介したのですが、私の年金額は税引き前で月額約20万円ですから、分配金から手にする30万円とあわせて、月額50万円ほどが生活費と見込めることになったのですが、それは欲張りなだけではなく、実際の生活費の必要に迫られての投資でもあったのです。
もし仮に、それが半分の1000万円の投資金額であれば、単純に私が実際に手にした2000万円での分配金の半分程度になり、反対に、3000万円を投資していたとしたら、おおよそ1.5倍の分配金を受け取っていた――このような、「取らぬ狸の皮算用」が成り立ちます。
そこで、実際に私が取った行動はというと、いまだ不足する分をなんとかさらなる分配金で補うべく、1つは、引き続きサラリーパーソン生活を続けることで、なんとか種銭を少しでも多く作り、投資に回すという選択でした。このあたりの経緯については前著で詳しくご紹介しましたので、ここでは割愛させていただきます。
ちなみに、昨年(2024年)の株価の暴落の時のことです。その頃よく耳にした言葉に、「絶好の買い場」というセリフがありました。