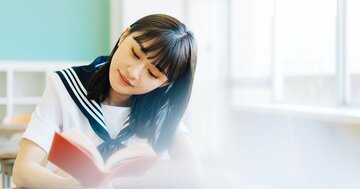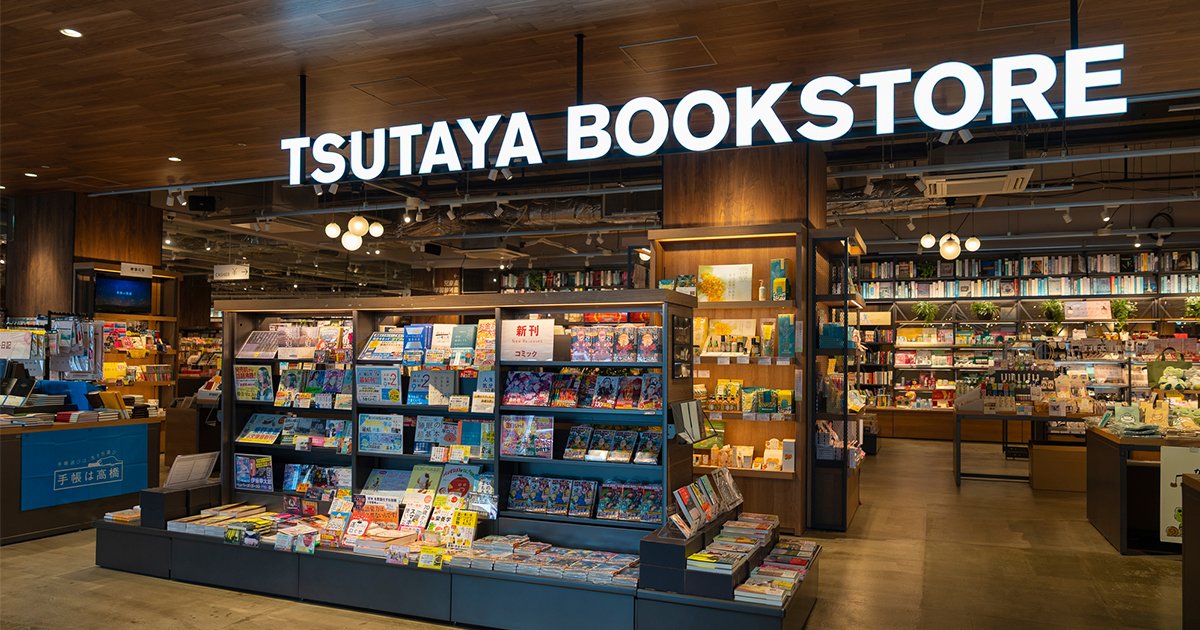 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
町の本屋には文房具や雑貨も売られており“本以外”の商品も扱っているのが常だ。そのほかにも、ビデオレンタルや深夜営業、カフェ併設などあの手この手で生き残りを図ってきた歴史がある。本屋が模索してきた経営戦略について、出版ジャーナリストの飯田一史氏が解説する。※本稿は、飯田一史『町の本屋はいかにしてつぶれてきたか 知られざる戦後書店抗争史』(平凡社)の一部を抜粋・編集したものです。
書店が郊外に激増したのは
複合化と夜型営業が鍵だった
能勢仁『書店経営のすべてがわかる本』(山下出版、1996年)は「商品の複合化で書店の経営革命が起こった」と書く。1980年代中盤の書店の粗利率は平均21.5%だが、ビデオレンタル導入書店では40%。1980年代から2000年代前半までは雑誌の黄金時代だったのに加え、レンタル業で書店への来店回数が底上げされ、「ついで買い」が大量発生した。
「書店経営」1997年10月号ではトーハン「平成9年度版書店経営の実態」を紹介しながら、売上高伸長率が書店専業店では前年比マイナス2.8%、AVレンタル複合店は3.4%伸長、セルCD複合店は1.9%伸長であり、粗利率は専業店21.7%、AVレンタル複合店40.1%、セルCD複合店26.6%と大差が付いていると強調、「年商2億円を超える店舗を維持していくためには、超大型専門店以外、複合店形態をとるしかない」と書く。
1980年代中頃から急激に店舗数を増やした郊外型書店の起爆剤は、複合化による書店経営革命だった。