1979年の国鉄部内発表会の資料によれば、高崎線は上野行きが15両編成9本、通勤新線直通快速列車が10両編成4本、川越線の通勤新線直通列車が10両編成4本(快速1本、各駅停車3本)、通勤新線の大宮始発が10両4本、通勤新線はあわせて快速5本、各駅停車7本と想定していた。
しかし、最大15両編成の高崎線に対し、通勤新線は設備上、10両編成が限度であり、輸送力の格差が混乱を招く恐れがあった。また、1984年に東北貨物線が赤羽まで旅客化され、東北線・高崎線の乗り入れが始まったことで宮原案は凍結となり、乗り入れ先は川越線に一本化された。
問題は東北線にもあった。東北線は大宮駅の線路配線の関係で通勤新線に乗り入れることができないため、上述の想定で、東北線は上野行きが15両編成9本、東北貨物線経由の池袋行が15両編成2本としていた。つまり、東北線と高崎線は別ルートで池袋方面に向かう想定だった。
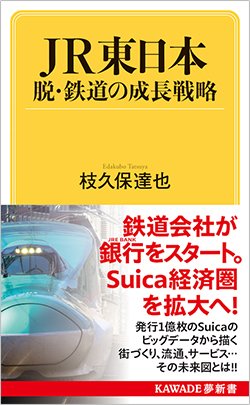 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
これでは分かりにくい。結局、東北貨物線の旅客化を拡大する方向に進み、1988年に乗り入れ区間が池袋駅に延長、2001年に湘南新宿ラインが運行を開始し、現在の運行形態が確立した。結果的に分かりやすく、便利な形に落ち着いたと言えるだろう。
話は東北新幹線に戻る。埼玉県の畑和知事(当時)は1977年12月、埼玉県議会で新幹線高架通過を容認する「最低4条件」として、通勤新線の建設、厳格な騒音対策の実施、新幹線全列車の大宮駅停車、大宮~伊奈間の新交通システム(ニューシャトル)整備を挙げ、歩み寄りの姿勢を見せた。
その後も埼玉県、東京都の沿線住民が工事差し止め訴訟を起こすなど、一部で対立が続いたが1984年に全ての裁判で和解が成立した。東北・上越新幹線は1982年に大宮駅をターミナルとする「暫定開業」をしていたが、大宮~上野間の工事が急ピッチで進み、1985年3月14日に延伸開業。半年後の9月30日に通勤新線改め埼京線が開業した。
埼京線はこのように新幹線と沿線住民、また高崎線と東北貨物線との複雑な関係を経て実現したのである。







