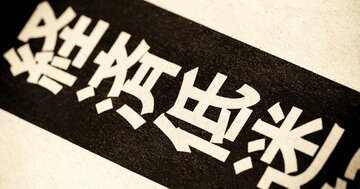もちろんスイス―ドイツの経済関係と、日本―中国の経済関係は中身がずいぶん違う。つまり日中間では経済の差別化・分業ができているといえなくはないが、今後は分業関係よりも競合関係が強くなっていくのではないか。
実際、中国に進出している日系企業向けアンケート調査(JETRO小林、2024)によると、中国市場における一番の競合相手は中国企業だ、と回答する日系企業の比率が80%を超えている。
つまり日本企業も意識的な差別化戦略をすべきで、スイスのクオリティ戦略からは学ぶところが多いといえよう。
日本人のデフレマインドが
企業の足を引っ張る
ここまで読まれた方の中には、日本もスイス同様高品質を強みとした国だから、いまさらクオリティ戦略をスイスから学ぶ必要はないと思う人がいるかもしれない。
しかし、これは筆者の私見だが、商品・サービスに関して、スイスが考える「クオリティ」と、日本の「品質」という概念にズレが生じている気がしてならない。おそらくこの背景には、日本が長年経験してきたデフレが消費者マインドに及ぼした影響があると考えている。
端的に言えば、スイス人にとってのクオリティとは、「ベストであること」「秀逸であること」を意味している。クオリティが本来意味するもので、価値起点の概念といってもよい。
日本人にとってもその通りだと思うかもしれない。ただ、デフレに長年浸ってきた日本人の場合、たとえば100円ショップで販売されている商品について、絶対的なクオリティは低いにもかかわらず、「100円にしては品質が高い」というような表現をする。
こちらは価格起点の概念といえる。コストパフォーマンス的な要素が入り込んでいる。
価値ではなく価格起点でクオリティを考えてしまうと、数百万円するスイスの高級機械式時計は、いかにそのムーブメント構造が秀逸で唯一無二であろうと、「(品質ではなく)価格が高い」となってしまう。
さらに企業がそのような消費者マインドに引っ張られてしまうと、「価格起点」でのクオリティは高いが、「価値起点」でのクオリティは必ずしも高くないようなものを生み出してしまう。